進捗状況 Vol.1
vol. 1 2025-01-22 0
ソトノノノの進捗状況をご報告します!
築100年の古民家を活気あるコミュニティスクール「ソトノノノ」に生まれ変わらせるプロジェクトが、着実に進んでいます!建設チームは、熱心な学生たちと共に、古い屋根瓦の撤去と張り替え、廃材の除去、建物の構造補強など、重要な作業を次々と達成しました。資材を手作業で運搬しなければならない遠隔地という厳しい条件にもかかわらず、床や外壁の解体、屋根の断熱工事、梁や柱の補強を無事に完了しました。
次のステップでは、地元の製材所である株式会社nojimokuと協力し、新しい床や壁を作り、トイレやシャワーといった設備を設置します。そして、持続可能で活気あふれるコミュニティスペースを目指し、さらなる開発に取り組んでいきます。キャンペーンの期間中、進捗状況や達成した目標についてのアップデートを随時お届けします。ここからの展開にもぜひご期待ください!皆さまの支援が、この素晴らしいプロジェクトの実現を可能にします。どうかご協力をお願いいたします!
一緒にソトノノノを完成させましょう!
〈屋根の撤去と新しい屋根の葺き替え〉古民家の屋根には、昔ながらの瓦とそれを支える土が使われていました。私たちは、瓦を1枚ずつ慎重に手作業で取り外し、土も土嚢袋に詰めて運び出しました。その結果、約2300枚の瓦と8トンの土を無事に搬出することができました!
2023年3月15日
2023年3月15日〈屋根の廃材を捨てる!〉
前回の作業では、屋根から下ろした瓦、土、杉皮、木材を捨てるための大作業を行いました。車が入れない敷地のため、まず30mほど手作業で運び、軽トラに積み込みます。その後、狭い坂道を慎重に下り、麓に駐めたダンプトラックに手作業で積み替えるという工程を約15往復繰り返しました。結果、瓦だけで4.84トンを搬出。捨てる作業だけで2日間を要するほどの大仕事でした!
2023年4月16日
〈床の解体〉バールを使い、荒板を次々と撤去していきました。最初は苦戦していた学生たちも、作業を重ねるうちにコツをつかみ、作業スピードが大幅にアップ!結果、すべての床板を1日で撤去完了。そのおかげで、これまで隠れていた土台の傷み具合も確認することができました。
2023年6月8日
〈外壁の撤去〉快晴の空の下、外壁の板材を次々と撤去していきました。30年以上空き家だったため、外壁や床下にはツタ植物がびっしりと絡みつき、撤去作業は大奮闘。ツタとはいえ直径3cm以上の硬い枝のようになっており、簡単にはいきません。それでも作業を進める中でチームはどんどん熟練し、最終的には外壁とツタを1日で完全撤去することができました!
2023年6月9日
〈外壁の張り替え〉東面と北面に波板を張る作業に挑みました。波板は、屋根の母屋や基礎の礎石の形状に合わせて、板金バサミで慎重にカット。胴縁のラインに沿ってチョークで墨出しをし、波板の山の数を数えながらひたすら釘を打ち込んでいきます。地味な作業の繰り返しですが、手を動かした分だけ目に見えて仕上がっていく達成感は格別です。最後の難関は、石垣と壁の隙間。どうやって釘を打つのかと思いきや、1人がペンチで釘をつまみ、もう1人が位置を指示、大工さんがカナヅチの側面を器用に使って叩くチームワークで見事に釘打ちを完了!
2023月7月19日
2023年7月20日
〈離れの解体〉古民家の脇には、崩壊寸前の離れがありました。かつてはトイレやお風呂、納屋として使われていた小屋です。
屋根にはツタ植物が繁茂し、独自の生態系を形成。なんと梁は植物に侵食され、もはや土化するほどの状態!自然の生命力には驚かされます。
そんな小屋を、一枚一枚瓦を下ろし、絡みついた植物を丁寧に取り除き、モルタルを剥がすなど慎重に解体。最後はロープで引き倒し、見事に作業を完了しました。
2023年11月12日
〈天井の断熱〉天井の一部を剥がし、そこから屋根の断熱工事を開始。垂木間の寸法を測り、それに合わせてスタイロフォームをカットし、ぴったり嵌め込んでいきます。11月の冷たい空気の中でも、屋根のガルバリウム鋼板に触れると北側はほんのり暖かく、南側はしっかり熱さを感じる――そんな微妙な温度差を体感しながらの作業でした。
2023月11月13日
〈柱と土台の補強〉建物の中心にある柱と土台が腐朽していたため、補強と修理を実施しました。まず、建物を少しだけジャッキアップし、新しい柱を既存の柱に抱かせてしっかり補強。束石も水平を丁寧に確認しながら据え直します。緊張感のある作業が完了した後は、土台をつなぎ直して根太をかけ、床の下地を作成。熟練してきた学生たちの手際の良さも相まって、作業はスムーズに進み、あっという間に完成しました!
2023年12月9日
2023年12月9日
2023年12月9日
〈床の修理〉母屋と増築部分は無理矢理つなげられているため、接続部分で雨漏りがひどく、床はフワフワ、グラグラ。いつ踏み抜いてもおかしくない危険な状態でした。
そこで床板を剥がし、際根太を打ち直して修理を開始。しかし、土台の形がいびつなため、際根太もグラグラする状況に。そこで際根太の下にもう一本根太(これも根太?)を追加し、ようやく安定感を取り戻しました。
試行錯誤を重ねながら、修理を無事完了。地味な前進ではありますが、達成感はひとしおです!
〈床の延長〉熊野の雨風にさらされ続けた影響で、玄関の建具とその周辺は腐朽が進行していました。今回は玄関としての復旧は行わず、室内の床を延長することに。室内床と玄関の高さを確認しながら、新たな土台を丁寧に設置。単純なビス留めではなく、相欠継ぎを施してしっかりと仕上げました。
〈昔の大工道具!?(番外編)〉古民家に残されていた埃まみれ、錆だらけの大工道具。少なくとも30年以上前のものですが、興味本位でノコギリやノミを試してみると…驚くほど良い切れ味!その性能に感動し、今回の改修作業に使わせてもらうことにしました。30年前の元住人も、未来に自分の道具が家を修復する役割を果たすなんて、想像もしなかったことでしょう。そう考えると、この道具を使うたびに感慨深い気持ちになります。
- 前の記事へ
- 次の記事へ
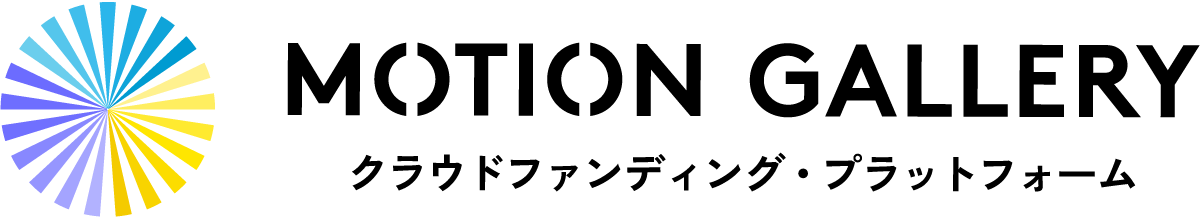
 FUNDED
FUNDED