\越境日記②(シナリオ編)/
vol. 6 2025-02-14 0
こんにちは、中の人の浅田です。
(飼い猫の頭と12月〜に借りたり買ったりした本です)
越境日記と題して始めたこちら。時系列を見返すために西山さんと交わしていたメールを見直しているのですが、西山さんとは全てメール(たまにオンライン)で打ち合わせをしていたので、LINEではできない謎の時空が発生していました。往復書簡ですね。
そして時系列にしていくと話題がとっ散らかりそうなので、今回はシナリオがどのように現在の『機械+新ハムレット(仮)』に決まっていったかの覚書を記していこうと思います。この辺りは、リターンのパンフレットでも詳細を触れていくつもりです。
2024.10.9-
シナリオについてどうするかの会話始まり。
尺は中編(30分〜)であることはすでに決めていたので、まず手段として①西山さん以外のどなたかとコラボしての新作シナリオ②西山さんの新作③既成シナリオ のいずれかにするか尋ねる。
そこで、西山さんから「イタリア式本読みの方法論からいって、既成の価値観とは違う何かしら新しい価値の創造を目指すものがいい」というキーワードが出てくる。また、撮影方法についてもどうするか考えるべきところ、という会話に。新しい価値の創造‥‥‥なんだろう‥‥
2024.10.12-
撮影手法はActing in Cinema(リハーサルと本番を同時進行でする)にする、で基本方針決定。
シナリオについてここからディスカッションが始まる。
出てきた作品:三島由紀夫『班女』
西山さん:『班女』をそのままやるのではなく、“『班女』を劇映画として撮ろうと試みる人たちの話”という構成はどうか?
浅田:舞踏(ex.大野一雄)などの身体の使い方もチャレンジしてみたい
2024.10.15-
『班女』をベースに他の題材も探す方針に。
浅田:「実験映画」と「新しい価値の創造」の違いは何か?
→いわゆる実験映画は技術や形式の実験が多い?西山さんの「実験」は芝居に関わることが基本。
西山さん:『野崎村』の中村鶴松の演技が印象的だった。歌舞伎と映画は相性が良いかもしれない。
2024.11.16-
『班女』をベースに他の作品をリミックスするのはどうか?
会話で出た作品:三島由紀夫『弱法師』『卒塔婆小町』『葵上』『金閣寺』
2024.12.7(オンラインmtg)
実はここで初めてオンラインmtg。企画メンバーで巻き込ませてもらった金岡くんも。
西山さんから紹介:谷崎潤一郎『お国と五平』坂口安吾『輸血』三島由紀夫『只ほど高いものはない』
2024.12.25-
ここで大きく方針転換。
三島由紀夫作品の「リミックス」が果たして著作権降りるのか?問題で、パブリックドメインの戯曲も進めることに。
浅田提案:横光利一『春は馬車に乗って』『蛾はどこにでもいる』
(『春は馬車に乗って』は、かつて私が所属していた劇団、京都ロマンポップの『幼稚園演義』という芝居の脚本でオマージュシーンがあり、横光利一の作品は元々好きだったのだがこの段になって急に思い出した)
この時期からすごい図書館通ったな〜。借りてたほんの一部。
2024.12.27-(この日は何回もメールやり取りしていた)
『春は馬車に乗って』は寝たきりなので動ける設定にしたほうがいい。
『蛾はどこにでもいる』は逆に移動が必要なので今回の規模で果たしてできるかどうか?
ここで西山さんから横光利一『機械』が出てくる。
(『機械』はもともと好きだったが、短編小説ということもありシナリオ化は無理だろうな、と思っていたので浅田の目が光る。)
西山さんから提案:太宰治『新ハムレット』はどうか?ただそれだとクローディアスが弱いので、志賀直哉の『クローディアスの日記』的要素を加える。
2024.12.29-
この辺りからクラウドファンディングのテキスト作成開始。プロジェクトをそもそも見直すいい契機になる。横光利一の妻モチーフの作品を浅田が西山さんに大量に送りつける。
(年が明けた!)
2025.1.16-
横光利一の妻モチーフの作品は動きが少なく難しい。
西山さんから提案:逆に『春は馬車に乗って』『花園の思想』と『機械』を足すのはありかも?=いや、『機械』の主人公を役者という設定にして劇団の話に作り直す?
2025.1.17-
『新ハムレット』を4名で構成し直す
+
『機械』を劇団内部の話にするのはいけそうだが、主人公の「彼」が受身的存在でドラマを背負わせることが必要。
→ここで、『機械』の主人公の劇団がやろうとしている演目が『新ハムレット』はどうか?という話題が初出。
10月時点で話していた『班女』をそのままやるのではなく、“『班女』を劇映画として撮ろうと試みる人たちの話”という構成はどうか?にも通じるものがあり、また、セリフの響きとしても、日常的なセリフと時代がかった散文詩のセリフが入ることでバリエーションが増えるのではないか、という話題になり、以後このスタイルをまとめていく形に入る。
所感
西山さんとのディスカッションで出た、ただそのまま脚本をやるのではなく、第三者的観点を入れたほうがいいのでは、というのは本当に目から鱗だった。演劇畑だったのもあるかもしれないが、2人芝居はそのまま2人芝居でやるものだ、という固定的な観念があったのかもしれないな‥‥(蛇足だけど、初めて映画美学校の講義で作品を作ろうとした時、この「撮っている」カメラはいったい誰なのか、はずっと考えていて答えが出てこなかったから、「インタビュー」という形式にした記憶がある。カメラは一体誰だ?)
そして、西山さんが急に「飛躍」するところに立ち会えたのはすごく面白かった。クラファンの企画そもそもを12月末から見直していたけれど、それが今回のシナリオ決定に大きく結びついたし、10月から話してきたこともとても大事だったんだな、と今見直していて実感。
最後に
機械 と 新ハムレット は青空文庫に所収されているので、よろしければぜひ読んでみてください。
X(旧twitter)で、このプロジェクトが達成しない場合は幻になる、といったお言葉をいただいて、とてもしっくりきました。幻‥‥本当ですね、幻‥‥All or Nothing方式って幻なんだ‥‥
プロジェクトで『機械+新ハムレット(仮)』に触れているのはこちら
https://motion-gallery.net/projects/nishiyama_project#c3
引き続き、どうぞよろしくお願いします!
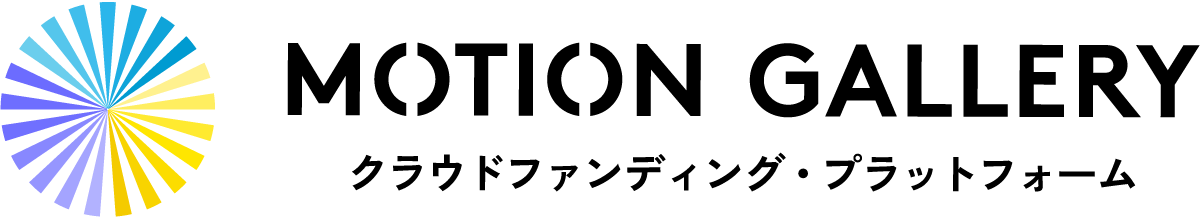
 FUNDED
FUNDED



