関野さんの近況が届きました!<旧石器時代からのつぶやき10>
vol. 26 2025-01-31 0
こんにちは!クラウドファンディング(以下、CF)担当スタッフです。
今回は「旧石器時代からのつぶやき」その10をお届けします!
以下、関野さんから届いた写真とメッセージです。
===
旧石器時代からのつぶやき10
2月から旧石器時代4番目のフィールド沖縄に行く。とても期待をしている。
今までのフィールド、奥多摩、新潟、北海道では、住居と食料という、そこで暮らす上で最も重要な事項二つが思い通りにいかなかった。沖縄では少しは私の期待を満たしてくれそうだからだ。
奥多摩では、試行錯誤の繰り返しで、私一人の家を完成させるために1年近くを費やした。家を石器だけで、鉄の斧、ナイフを使わずに建てるわけだ。石器を作り、ひもを綯い、木を切り、皮を剥ぐ。草木にも竹を切り、草を刈る。野生の草木にも旬があり、いつでも切ったり、剥がしたりできるわけではない。例えば杉の皮は屋根材として優れている。ところがいつでも剥がせるわけではない。一年で一番水を根から幹や枝に吸い上げるのは梅雨時の一ヶ月ほどだけなのだ。その他の季節は、「剥がせるものならはがしてみろ」と嘲るように、びくともしない。後一年待つしかないのだ。葦や千萱、ススキも刈るのにいい季節がある。土屋根が魅力的だが、屋根の傾斜が緩やかでないと、土が滑り落ちてしまう。緩やかだと雨に弱いのだ。
沖縄では、家はどのようにつくるのか? 作らなくてよいのだ。洞窟がたくさんあるからだ。
沖縄のガマと呼ばれる自然洞窟は有名だ。ガマは洞窟の沖縄方言だ。戦時中日本軍によ る陣地壕、野戦病院、住民の非難壕として使用された。ガマによっては火炎放射器で焼かれた跡や、遺品、 遺骨などが散在しており、沖縄戦の「もの言わぬ語り部」として認識されている。洞窟遺跡も多い。洞窟遺跡や沖縄戦の遺構は使えないが、自然洞窟はたくさんあるらしい。
わたしが住める洞窟があれば、家づくりの手間が省ける。縄文時代は栗などの栽培をし、定住するようになった。一方で狩猟・漁労・採集民だった旧石器時代人は栽培をしない遊動民だったので、岩陰や洞窟を使ったと思われる。日本ケイビング連盟会長で、洞窟探検の第一人者である吉田勝次さんによれば、西表島や石垣島には住める洞窟がたくさんあるという。彼自身も沖縄の洞窟をいくつも探検しているが、彼の同志がたくさんいて洞窟探しを支援してくれることになっているので、楽しみだ。
2025.1.29 石器野吉晴
(写真は、これまでの住居。山熊田、奥多摩、二風谷)
===
いかがでしたか?
いよいよ次の舞台へと遊動する関野さん。
続きをお待ちください!
◆関野吉晴 Instagram
https://www.instagram.com/yoshiharusekino/
↑こちらにも掲載されています。
また、Xにも、旧石器時代タイムトラベル計画の専用アカウントがあります。
随時近況を発信していきますので、ぜひフォロー&いいね!拡散!などで応援をお願いします!
◆関野吉晴 旧石器時代タイムトラベル計画 公式X
https://x.com/sekinokyusekki
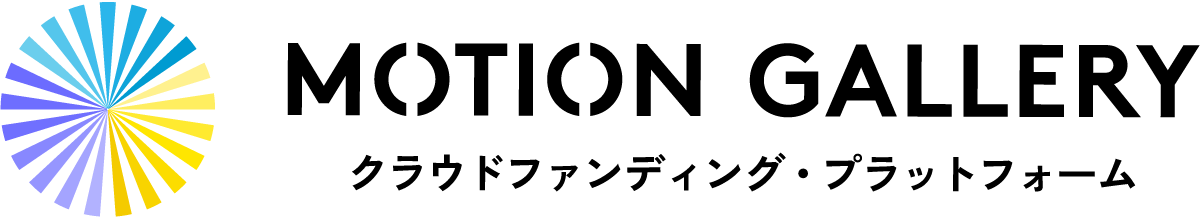
 FUNDED
FUNDED



