残り7日「地域の不動産データをどう活用する?」
vol. 24 2025-03-18 0
残り7日。田舎の不動産を“見える化”するには?
クラウドファンディングも終盤に入りました。
ここまで、空き家の活用、新築とのバランス、地域で生まれる仕事の可能性などを考えてきましたが、
どの問題にも共通して言えるのは、 「田舎の不動産は情報が見えにくい」 ということです。
例えば、こんな経験はないでしょうか?
・「この空き家、活用できるのかな?」と気になっても、持ち主が分からない
・ いざ売ろうとすると、手続きが複雑すぎて断念する人が多い
・ 行政や自治会が空き家対策をしたくても、データが整理されていないため動きにくい
つまり、 情報が断片化している ことが、空き家問題を解決するうえでの大きな障害になっています。
この状況をどう変えるか?
鍵になるのは 「自治会・行政・不動産の連携」 です。
本日のテーマ:「地域の不動産データをどう活用する?」
◆ 田舎の不動産が“見えない”理由
都市部では、SUUMOやアットホーム、レインズなどの不動産情報サイトを活用すれば、
「どんな物件が売りに出ているか」が一目で分かります。
しかし、田舎の不動産は 市場に乗らず、水面下で取引されることが多い ため、
地域外の人にとっては 「そもそも選べる状態になっていない」 のが現状です。
具体的には、こんな問題があります。
- 空き家の持ち主が分からない、連絡が取れない
→ 地元を離れてしまい、誰が管理しているのか不明なケースが多い
→ 相続が進まず、所有権が曖昧になっている - 情報がバラバラで、整理されていない
→ 登記情報が古い / 役場と不動産業者の情報が一致しない
→ 空き家バンクがあっても、最新情報が反映されない - 行政・自治会・不動産業者の連携が弱い
→ 行政は調査できても、売買の手続きには関与しづらい
→ 自治会は問題を把握していても、不動産業者に情報が届かない
この結果、 売りたい人と買いたい人がマッチングできず、空き家は放置される という負のループに陥ってしまうのです。
◆ 不動産の「見える化」には、地域の協力が不可欠
この課題を解決するには、 単なるデータベースの構築ではなく、「地域の協力体制をどうつくるか」が重要です。
僕が今、自治会や行政との連携を進めているのも、
「不動産業者だけでは解決できない」部分を、 地域の力で補う仕組みをつくるため です。
田舎の空き家問題は、不動産会社だけでなく、
自治会や行政、さらには住民自身が協力することで初めて前進します。
具体的には、以下のような 「三位一体の仕組み」 を構築することが必要です。
① 自治会:地域のリアルな情報を集約する
・ どの空き家が問題になっているか、地域住民が把握している情報を集める
・ 役場や不動産業者と連携し、売却・活用できる物件を明確にする
・ 住民に「使える空き家」「使えない空き家」の判断基準を伝える
② 行政:データを整備し、活用できる環境をつくる
・ 空き家所有者の情報を整理し、自治会や不動産業者と共有できる仕組みを整備する
・ 既存の空き家バンクをアップデートし、使いやすいものにする
・ 「所有者不明土地」問題の対策を進め、活用できる土地を増やす
③ 不動産業者:実際の売買・マッチングをサポートする
・ どの物件を市場に出せるか判断し、売買や賃貸の手続きを進める
・ リノベーションや新築の選択肢を提示し、「住みたい家」にする
・ 住民と外部の移住希望者をつなぎ、「地域の資産」としての価値を再発見する
この3つがうまく連携すれば、 「空き家が放置されるだけの土地」から「選択肢がある土地」へと変えていくことができるはずです。
◆ デジタル×アナログの融合がカギになる
さらに、この仕組みをより機能させるために、 「デジタルツールの活用」 も不可欠です。
さとまる不動産では、 地域の空き家情報をデジタルに簡単に起こせるツールを開発し、
自治会や行政と連携しながら 情報の取得と活用を容易にする仕組み を作ろうとしています。
・AIを活用し、空き家データを音声入力で簡単に管理できる仕組み
・登記情報と連携し、所有者にスムーズに連絡できるシステム
・住民がスマホで写真を撮るだけで、自治会や不動産業者が状況を把握できる仕組み
これらを 地域のリアルな情報と組み合わせる ことで、
田舎の不動産市場は「選べない」状態から「選べる」状態へと変わっていくのではないでしょうか。
◆ さとまる不動産が目指すもの
僕たちは、田舎の不動産が 「誰にも管理されず、ただ朽ちていく」 のではなく、
「住みたい人、活用したい人が選べる状態」にすることを目指しています。
□ 自治会・行政・不動産が連携し、情報の透明性を高める
□ デジタルツールを活用し、住民自身が関われる仕組みをつくる
□ 「売る」「貸す」「活用する」という選択肢を持てる環境を整える
こうした仕組みを江田島でモデルケースとして構築し、
呉市のとびしま海道、東広島市の福富町、尾道市の向島など、似た地域へと広げていくことができると考えています。
◆ 現在の進捗
・支援金額:671,000円(67%達成)
・支援者数:52人
・終了まであと8日
このクラウドファンディングが、「田舎との関わり方の選択肢」を広げるきっかけになれば嬉しいです。
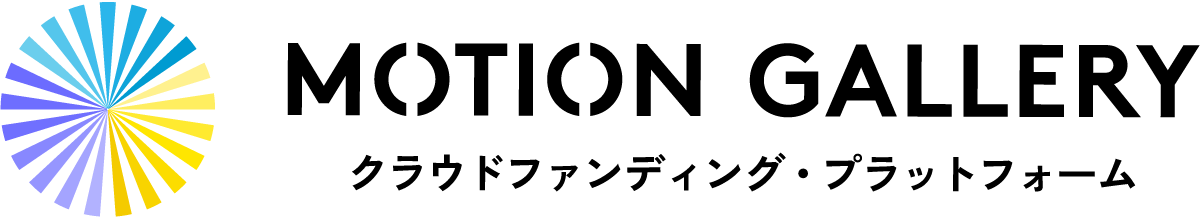
 FUNDED
FUNDED



