残り8日「田舎の価値は、誰が決めるのか?」
vol. 23 2025-03-17 0
【残り8日。田舎の未来を本気で考える時間。】
クラウドファンディングが残り9日となり、ここからは「田舎の未来をどう描くか」という核心に迫りたいと思います。
これまでの投稿で、僕は田舎の不動産活用の可能性について語ってきました。
しかし、今問いたいのは、「そもそも田舎の価値とは何か?」ということ。
そして、その価値を決めるのは誰なのか。
都市と地方の格差が広がり続ける今、「田舎の可能性」と言いながらも、実際には活用されない空き家が増え続け、誰もが関心を持つわけではない。
では、田舎に眠る価値を掘り起こし、未来につなげるために、僕たちはどのような視点を持つべきなのか。
今日は、「田舎の価値は誰が決めるのか?」という視点から、このテーマを掘り下げていきます。
本日のテーマ:「田舎の価値は、誰が決めるのか?」
◆ 田舎の価値は、流通しないと生まれない
都市部の不動産市場は、駅からの距離や築年数、間取り、周辺環境といった指標で価値が決まります。
しかし、地方の不動産はこの「市場の論理」だけでは計れません。
同じ築50年の住宅でも、都市部ではリノベーションされ高値で取引されるのに対し、地方では無価値とされることが多い。
この違いを生むのは、「その物件が、適切に流通しているかどうか」です。
市場が機能しなければ、価値は認識されず、結果的に「負動産」となってしまう。
田舎の不動産の最大の課題は、「価値がない」のではなく、「価値を認識する人がいない」ということ。
つまり、田舎の価値は、市場の中で適切に流通することで初めて生まれるのです。
◆ 田舎の価値を再定義する3つの視点
田舎の不動産が「負の遺産」にならないために、以下の3つの視点を重視するべきだと考えています。
① 暮らしの価値を見直す
都市部のような利便性はないが、田舎には「豊かな時間」「自然との調和」「地域のつながり」といった価値がある。
ただし、これらは「憧れ」だけでは成り立たない。
地方に移住しても、「生活の場」としての環境が整っていなければ、人は定着しない。
“田舎暮らし”を成り立たせる生活基盤が、田舎の価値を決める鍵になる。
② 景観と文化の価値を再評価する
田舎の風景や建築は、「経済合理性」だけで評価されるべきではない。
歴史ある町並み、地形と調和した家屋、伝統的な建築様式は、次世代に引き継ぐべき資産であり、まちのブランドを形成する要素でもある。
「保存すればいい」という話ではなく、「その土地にしかない風景をどう残すか」という視点で、活かし方を考える必要がある。
③ 新築を、田舎の新しい選択肢にする
田舎には「古い家しかない」という状況が多い。
しかし、新しい住まいが提供されなければ、移住者や地域の若者が「住みたい」と思える環境が生まれない。
ただし、都市のような「画一的な住宅」ではなく、その土地に合った新築を建てることが大切。
「新築=都市化」ではなく、「新築=土地のポテンシャルを引き出す手段」として考えるべきではないか。
◆ 田舎の不動産の意思決定者は誰か?
空き家の運命は、基本的に所有者が決める。
しかし、所有者はその家の「今後の最適な使い方」を知っているとは限らない。
結果として、「売るに売れない」「貸すに貸せない」「壊すに壊せない」といった状態で放置されるケースが多い。
これを解決するためには、地域全体で「どこを活かし、どこを更新するか」の意思決定をする仕組みが必要になる。
・ 行政と民間が一体となり、空き家の情報を集約・整理する
・ 地域住民と共同して「活かす家」と「手放す家」を明確にする
・ 不動産事業者が、どう活用できるかの選択肢を提示する
個人の判断に任せるのではなく、地域の視点で「最適な形」を探ることが、これからの田舎の不動産には不可欠ではないでしょうか。
◆ さとまる不動産が目指すもの
僕たちがやりたいのは、単に空き家を活用することではなく、「田舎で暮らす人が最適な選択肢を持てる状態をつくること」です。
□ 活かせる空き家は、適切に再生する
□ 新築が必要な場所には、その土地に合った価値ある建物をつくる
□ 地域全体で、適切な活用を決めていける仕組みをつくる
田舎の価値は、所有者だけが決めるものではない。
地域の未来に関わるすべての人が、「ここに住みたい」「この場所を活かしたい」と思える環境をつくることで、はじめて生まれるのではないかと思っています。
◆ 現在の進捗
・支援金額:671,000円(67%達成)
・支援者数:52人
・終了まであと9日
このクラウドファンディングが、「田舎との関わり方の選択肢」を広げるきっかけになれば嬉しいです。
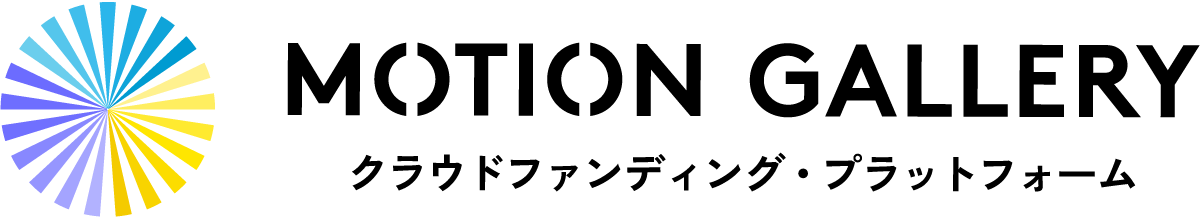
 FUNDED
FUNDED



