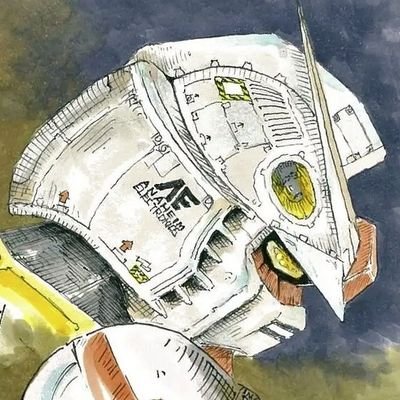【王子戯曲同好会④】劇場蔵書 永井愛「ら抜きの殺意」
vol. 35 2020-04-13 0
言葉というものはどうにも厄介なもので、時折わからなくなる。人によっては読めなくなったり聞き取れなくなったりすることさえあるようなのだが、自分の身に瀕した様々な危機的状態によっても、言葉によって受け取るのではなく、なんとなくのニュアンス・言葉に伴う(連想される)表情・文脈上こう飲み込んで反応すれば問題ないという短絡的な理解をもって、それとなくやり過ごしているにすぎないという事も多々ある。言葉を介しているようで言葉を不要(不急ではない)にしてさえいる。
ボクの言葉はボクの理解を通して語られるものであり、ここから実感が遠のくとなお危ないように思える。理解ということさえ、上述と同様の朧さを持つ。SNS社会に対する関心を、大学に通っていた頃を契機に強めるような気取りさえ抱えてきた身の上で、ボクの理解というよりボクから分離して作られた、「ボクの脳のコピー」でしかアカウント――そもそもは識別のためのIDのようなものが、あるいは多くの人たちにとって、子供のように育てられることに専念され、そして子育てに失敗したように暴走していく。人によっては、この個人の実体的な存在さえ本当は希薄な世の中で、確かに存在するアカウントに人生を多く分配し、遅れてきた反抗期のような、自分育て、俗にいうブランディングやセルフプロデュースを荒ぶらせているようにさえ見受けられる。確かなものはアカウントの人格なのか、飲みに行った時に話す目の前のその人なのか。恐らくともに確かに存在しており、またそれらが全く根を別にしているというのがボクの見解だ。その下にボクなりに戯曲について以下へと徒然になぞっていく。
永井愛「ら抜きの殺意」では、題名どおりに、他人の司る言葉、ツールとして存在しているものに対して、現実的な感情のリアクションをもって、不快感を覚えて(本作では、現実なんかより一層にコミカルに)殺意まで抱いた人々を、ちょっとした2つの日常のスパイスで翻弄する物語だ。そのスパイスのうちに、個々が抱える「架空的な人格の概念とはまた別の、避けがたい当人の事情」が浮き彫りにされ、時に人間関係の主客転倒が起こり、時に言葉で説明するまでもない行動が起こされ、誰かしらが困り、また時に受け入れる。
言葉遣いは恐らく一般的に、教育によって矯正されるものだ。本作の主人公とも言える、とある物販会社にアルバイトとして急遽飛び込んできた海老名は、お金に困り(アルバイトが禁止の公職である)国語教師を続けながら、様々な言葉の混然とする場にどうにも落ち着きを得られない。人間の習性として、人間は可能になるなら自身の落ち着きを得られる方向に環境を適応するのに従い、そりの合わなかった先輩社員 伴の言葉を矯正し始める。海老名の用いた正当性のロジックの主旨は、言葉遣いを改めれば営業にも活きる、という、社員としての記号としての≒伴の存在にも向けられている。もちろんそれより希薄でありながら、同僚としての伴が自分にとって居心地のよい言葉遣いの者になり、そうした者の集いを教育してより心地の良い職場を作ろうとするのだが、こうした王国創設譚に物語が帰結するかというとそうではなく、教職している者としての立場を嗅ぎつかれ、伴に反旗を翻された彼は、今度伴の認識にとって当たり前だった言葉遣いを教育されるようになる。完全に言葉遣いが入れ替わった瞬間の彼らはあべこべで、猪のフリをするアヒルのような可愛らしいユーモアを湛えている。
言葉に注念して他人を教育しようとするのは、理に適っているようで適っておらず、その末路というか、その論理が通るのであれば考えうる選択肢として、滑稽もといユーモラスな状況を生み出すに至る。それが赤の他人、海老名のようにより広く社会の為になど言い始めると、そうした状況で混乱する人が出てこないわけがない。この物語では、その「混乱」が確かに面白く、また考えさせられる展開になっている。
劇作的なところに焦点を当ててみると、随所で小気味よく挿入される「口喧嘩」が絶妙な舌鼓を誘発させる。ボクのこれも感覚として断る点として、ボクは会話劇において、口喧嘩はハリウッド映画や時代劇におけるアクションシーンであると考えている。小さい口喧嘩から大きな口喧嘩まで、とても気持ちよく(かっこよく・おもしろく)読み手を楽しませるものになっているのには目を瞠る。色んなキャラクターによる、バトルシーンがここにはある。そしてこれが、能力者バトルもののに通ずるようにだいぶ色濃く特殊な人々であり、その書き分けがよくなされているものだから、少年漫画好きのボクの少年漫画好きな面が似たものと認識してするすると読めてなどしてしまった。もちろん、気取って学術書好きなボクがところどころで知的好奇心を刺激されるような社会風刺が、通奏低音として敷かれていることで、文字戯曲ならではの「いちいち立ち止まって読める良さ」も折り紙つきだ。
鶴屋南北戯曲賞第一回受賞作、というこの本をボクは大学生の頃にも読んでいて、自分の代わりに何かを刺すような、風俗的な見方の整理に、ボク自身は楽しく読めている。ここで築かれた風刺が的確であるからこそ、その延長線上で、まんまと悪化あるいは混沌化していっている世の中を、変に入り込んで悲観してみせるのではなく、余裕を持った観点からシリアスぶらずに身の置き方を自問することができる。
こうして書いていると嫌いな人間の事を思い出しなどする。そうした事は書く必要も無いのだろうが、不要不急でない事しかしてはいけないわけではないのがこうした執筆の醍醐味で、問題は書き方だけであると自認しているので、何の問題も感じていない。
永井愛作品の登場人物は知的だ。知的な人間とボクが友達になりたいという意味において。また、知的という意味がわからないと言われても、辞書を引けばわかるよなんて言えないところに、ボクは何かを書き続ける意味も感じている。
永井愛さんはもう御年70近いわけだが、未だに新作を卸してご自身の持つ劇団「二兎社」で公演を打ち続けるなどしている。その二兎社も先月、このコロナ感染拡大の影響により、公演中止の判断をくだしている。
※1998年 而立書房出版
永井愛『ら抜きの殺意』
劇場を窓口に、クラウドファウンディングをしています。
とにかく健康でみんなにいてほしいとばかり最近思います。
アイコニックな生き方は暴走しがちな中、現実世界が健康になる事を心より祈っていますという(等身大の収まりつかない)ボクの話と永井愛「ら抜きの殺意」のお話でした。纏めようとしてばっかり。
今日の残りも明日も元気にやっていきます。ファイトオー。
P.S.
笠浦さんからお借りしていた、この王子戯曲同好会第一弾で紹介された別役実「虫づくし」を読了しました。とても面白かった、です。くすぐられるような、というのはコミカルな作品に対してよく使われるものですが、体の希少部位を出し抜けにくすぐられるような本でした。別役実、油断ならず。基本虫に関するホラ話で構成されている本書ですが、特にハチの話では、イメージの遠いところまで飛躍していっているようで、物語全体が巧妙な比喩のようになっているのをずしんと受けた説でした。つまりは、抱えきれない、よもや理解できている感の特に淡い、遠くに別役実を感じられる読書体験をプレゼントしてくれたのでした。随所に挟まれている注釈も滑稽で、こおろぎの話を逆さ読みにするとどうなるのかを説明してくれるのに、それで何が起こったり何が問題だったりするわけでもないと、遠くにいると思ったら意外と近くにいた、といういないいないばあっ! みたいな話運びにに惚れ惚れしました。別役実さんみたいな人は好きだな、と読書の恋心揺れるような一冊でした。笠浦先輩、ありがとうございました! まだお返しできてなくてすみません、次お会いした時には必ずや! 今度ボクも何かお貸しできたらと思います!

 FUNDED
FUNDED