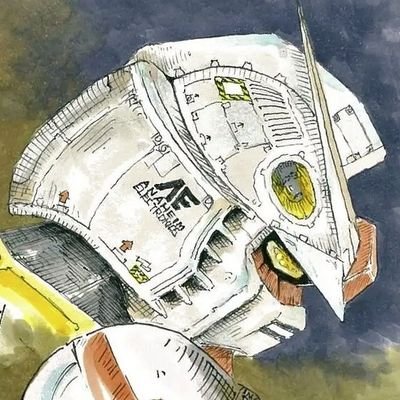【王子戯曲同好会③】あつまれ!チェーホフの森(チェーホフ 一幕戯曲を全解説)
vol. 26 2020-04-04 0
笠浦です。戯曲同好会②のコラムにおいて、平井君が自分はインテリじゃないのでとあんまり強調するもので、これは私に対するなんらかの当てこすりか、遠回しの警鐘ではないかと不安になったわけですが、まずはこちらをお聞きください
沼野充義(東京大学教授)最終講義「チェーホフとサハリンの美しいニヴフ人――村上春樹、大江健三郎からサンギまで」
私の敬愛する東京大学教授の沼野充義教授が3月をもって定年退職されました。その知識の幅広さ、見解の深さ、あらゆる言語に精通する語学力、世界を飛び回るフットワーク、また温厚なお人柄を熱烈に尊敬しておりますし、実際私の稽古場の人間の何人かは「素敵な人」の例としてこの沼野教授を検索させられたことがあります。単に私がファンってだけじゃなくて功績も経歴もほんとにすごい人なんです!東大ご退職後は名古屋外国語大学にて教鞭をとられるとのこと、さらなるご活躍を楽しみにしてます!
そんな沼野教授の最終講義、新型コロナの影響で一時は中止が決まりましたが、まさかの生配信決定、当然観ましたし、「これは最終講義ですが、最新講義です」の言葉からはじまるものだからそれは泣きますよね。
特に後半のサンギのインタビューのくだりは資料としてあまりに貴重、かつ感動的。全編通じてとても平易な内容なので、ぜひ見てください!(真のインテリの言葉とは、こんな風に、誰にでも理解できるものなのではないのか、平井君よ)
いつまでアーカイブを残していただけるかわからないので是非いまのうちに。講義は90分、そのあとの質疑応答も大変すばらしいです。
講義中触れられているチェーホフ『サハリン島』は、旅行記というか調査記録というか、文学作品としては異色のものではありますが、チェーホフ自身の創作の転機となった点で重要であり、また時代柄、アイヌだったり日本だったりにも言及があるので、興味深く読むことができるかと思います。
チェーホフは医者であり、「医学が本妻、文学は愛人」と言い切っていましたから、もしも現代にチェーホフが生きていたとしたら医療のほうに全精力を傾けていたに違いないのですが、医者ならぬ私は一体どう生きるべきなのでしょうか。
とりあえずここで蔵書自慢をさせていただきます。
じゃーん!
私の6畳しかない自宅にはいかにも不釣り合いな、愛すべきチェーホフ全集(全16巻。中央公論社)です!!
私にできることと言ったら、せめて外出できないみなさまに、こちらから戯曲を紹介することくらいです。沼野教授のように弁舌さわやかにとは参りませんが、自称チェーホフガチ勢の私が、以下、精一杯ご紹介いたします!
『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『桜の園』…名作。みんな読み、そして観てね。
このへんもうしゃべっても仕方ないのでこれで済ませます。上演が差し控えられる時勢ですが、いろんな文庫版、多数の翻訳があるので気に入ったものをどうぞお手にとってみていただきたい。翻訳は私は神西清訳が最高だと思いますが、シェークスピア好き!みたいな方ですと、小田島雄志翻訳もあるのでそっちがとっつきやすいかもしれません(小田島さん素晴らしいけど、ロシア語はできないので英語版からの重訳)。
チェーホフの多幕の戯曲にはほかに以下のようなものがあります。すべて先にあげたいわゆる四大戯曲よりも前に書かれたものです。書かれた順に。
『プラトーノフ』(1880ごろ?)(同全集14巻)
未発表戯曲。推定としてはチェーホフの学生時代に書かれたいわゆる習作であると思われる。発見された当初は自作の11冊のノートにびっしりと書かれていて題も不明。チェーホフの死後1960年に上演されるにあたって、主人公の名前からとってこういう題になったのです。
『イワーノフ』(1887第一稿、1889最終稿)(同全集12巻)
ロシア文学伝統(?)のいわゆる「余計者」が主人公のやつです。イワーノフは借金もあって鬱っぽくなってます。1887年の初演は賛否両論で、拍手喝采と野次が同時に巻き起こったとか。その後結末を含めて2度も書き変えられ、1889年の再演ではより好評を博しています。この再演の成功がチェーホフを励まし、同年に『森の主』を書きます。
『森の主』(1889)(同全集12巻)
モスクワ小劇場文芸委員会より「上演には不適当」として突っ返された戯曲です。これが改作されてワーニャ伯父さんになったので、かなり共通のセリフがあります。目立つ改作部分としては『森の主』では伯父さん役が自殺しちゃうのに『ワーニャ伯父さん』では生き残ったってとこですね。あと『森の主』ではわりとかわいいと描写されてたソーニャちゃんが『ワーニャおじさん』では不細工です。ソーニャ好きの私としてはつらい変化ですが、痛いほど効果的な変更点です。この2点の変更があればこそ、あのワーニャ伯父さんの比類のない美しい幕切れのシーンが生まれたわけですね。話それますけど、あのソーニャのラストの一言、原文「Мы отдохнем」、直訳すれば私たちは休む、というのを、「ほっと息がつけるんだわ」って訳した神西清はやはり天才なのではと思います。
いえ、しゃべりすぎていますね。違うのです。四大戯曲に関することなら正直名のある方がもっと効果的に評論されてますのでそちらをご覧くださいませ。私が言いたかったのは、これに加えて愉快な一幕ものもあるんだよ、ということです。
チェーホフは44歳の若さで亡くなったので、そんなに量もないことですし、書かれた一幕ものに関してはすべて解説します。()内に執筆年と収録されている全集の巻数を付記します。
『白鳥の歌(コロス)』(1887)(全集11巻)
飲みすぎて寝てたら夜になって、劇場にうっかり閉じ込められてた老役者と、こっそり楽屋に寝泊まりしていたプロンプターの中年男による演劇談義です。上演したら20分くらいでしょうか。シェイクスピア『リア王』『ハムレット』『オセロ』やプーシキン『ボリス・ゴドゥノフ』『ポルタワ』、グリボエードフ『智慧の悲しみ』からの引用が見られます。
さて、チェーホフの『かもめ』について、清水邦夫の『楽屋 -流れさるものはやがてなつかしき-』で知ったよ!という人もいるかもしれません。『白鳥の歌』は設定・構造として『楽屋』にとても似ています。ただ『楽屋』が女優の、場所に染みつくような業を描いたものだとすれば、こちらはもっと乾いた何かです。役者という浮かばれない商売の悲哀と、演じることのつかのまの快楽が、どうしようもないなかでもサラリと描写されていてなかなかカッコいいです。『楽屋』が好きな方にはぜひ読み比べてみていただきたいです。
『熊』(1888)(同全集11巻)
こんなポップな話がなんでもっと頻繁に上演されないのかなあ、と思います。最愛の夫を亡くし悲しみにくれて家から一歩もでない若き未亡人と、それを励ます老従者。そこに現れたのは亡夫からの借金を返してほしいという、熊のような野蛮な男。未亡人は、そんな金は知らないしいまは支払えないと弱々しく言うのですが、男はそこに居座ってしまいます。未亡人もだんだん腹が立ってきて、男と壮絶な言い争いに発展します。ついにこれはもう決闘だ!となって、未亡人はお前の頭をぶち抜いてやるだとか威勢よく吠えるのですが、その勇ましいこと、惚れ惚れします!男のほうは実際にそれに惚れてしまって、意外と未亡人もまんざらでもなく、最後は幸せなキスをしておわり。ちゃんちゃん(笑)
これかいたときチェーホフ私と同い年の28歳なんですよね……。
『プロポーズ』(1889)(同全集11巻)
これは上演されてるのも観たことあります。キャストも3人でとっつきやすく、会話も楽しい、老いも若きもごうつくな人間たちの可笑しな話。「娘さんをください!」と言いに来たはずの男が、ちょっとした話の流れから、その当の娘さんとその父と、やれあの土地はうちの家のだそっちの家のだ、うちの犬はお前の犬より優れている、いや劣っていると、大変些細なことで口汚いけんかをします。そのやりとりはほんとにしょうもなくて、多分にデフォルメのきいた描写だとは思うのですが、見方を変えてみれば、ロシア帝政末期における地方の地主たちのメンタリティについての貴重な記録といえるかもしれません。結局、農奴解放令なんて、地主にも農奴にも災難だったみたいなことを『桜の園』でフィールスが言ってましたが、この土地と人の間の複雑な関係とそれにまつわる人や金のからみによるフラストレーションって、ロシア革命の遠因の一つには確実になってると言われています。チェーホフが亡くなったのが1904年ですから彼は帝政末期までしか生きていないのですが、翌年には血の日曜日事件で帝政が大きく揺らぎ、17年にはロシア革命です。もし革命後も存命だったら、いったいどんな作品を書いていたんでしょう?
『心ならずも悲劇の主に』(1889)(同全集11巻)
短編『ざらにある話』(1887)を改作したもの。
ロシア人というのは伝統的に(そして今もなお)別荘を持ちがちです。
これは別荘暮らしをしている妻子持ちの男が、独身の男のところに訪ねていって、ひたすら愚痴を言うという、それだけの構成になっております。最初は、そんな細かいことでごちゃごちゃ言うなや!という気持ちで読みますが、最終的に友人に対して発狂してしまう男を笑っていいやら、明日は我が身ととらえるべきやら、微妙なところです。もちろんこれは笑劇として書かれたものなんですけど、こういう、生活のほんとにとるにたらない疲弊が積もり積もって人を狂わすっていうのはブラック企業勤めのメンタリティとも通じていてぞっとするところがあります。今作はまだ平和なラストですが、同じようなテーマで名作短編『ねむい』のほうはかなりセンセーショナルな展開なのでそちらもぜひご一読いただきたい。
『披露宴』(1889)(同全集11巻)
その名の通り披露宴中の話。文句ばっかり言う新郎とか、やたら歌がうまい助産師とか、この披露宴に将軍を呼ぶと約束したばっかりに右往左往する人と、将軍のふりをさせられる耳の遠い老人とかが出てきます。モチーフが多くてただただ楽しい。そして、みんなで乾杯して、周りが「(酒が)苦い!苦い!」とはやし立てて新郎新婦をキスさせるところとか、結婚の風習の描写に心躍るものがあります。
ほとんどロシア語のわからないギリシャ人の菓子職人が出てくるんですけど、彼は「ギリシャに伊勢えびはいるの?」とか「マッコウクジラは?」とか「しいたけは?」「まつたけは?」とか聞かれ続けるんですが、全ての質問に「ある。ギリシャにはなんでもある」と答えます。こいつすごく好きなんですよね。基本、ギリシャにはすべてがあって、ロシアには何もないらしい。
でもまあこのギリシャ人の言うことにも一理あって、時代的には欧州ではとっくに電灯の明かりがともるというのに、近代化に100年遅れたロシアはいまだに火を焚いて結婚を祝っているのです。広大な田舎としてのロシアという風情が感じられます。
『創立記念祭』(1891)(同全集11巻)
ポリティカルコレクトと男女同権の観点から言うと、現代での上演にはちょっと言い訳を添える必要があるかもしれません。舞台は銀行。理事長と女嫌いの銀行員が、今日の創立記念祭に向けて目の回るような忙しさのなかで仕事をしています。そこに現れるのは理事長の若い奥様と、請願書を持ってきたご婦人です。若奥様はずっとぺちゃくちゃぺちゃくちゃとりとめがないし、ご婦人の請願はものすごく筋が通らないしで、ついに女嫌いの銀行員が激昂してしまい、彼女たちを口汚く罵り、もうパニック状態。そこに創立記念祭の祝詞を述べるために燕尾服の代表団がやってくるのですが、あたりはすっかりめちゃくちゃ……。
要は、バカの相手って死ぬほど疲れるよね、みたいな話ではあるのですが、この全然話の通じないバカ代表みたいな若奥様がすごくチャーミングです。短編『可愛い女』のオーレンカみたいな感じ?私このチェーホフに出てくる考えの全然ない女の子たち、かなり好きなんです。
『タバコの害について』(1886~1902)(同全集11巻、14巻)
登場人物は燕尾服姿の男一人。田舎のクラブの演壇に立っています。タバコの害について演説するはずが、いつのまにか話は生活やら奥さんが怖いやらに飛び、本題にはほとんど触れないまま終わってしまう、という滑稽なボードビルです。たったそれだけの話なのですが(それだけの中に一人の男の全人生が詰まっているのがすごいことなんですが)、これ一度新聞に発表されたのちに6回も書き改められているんですよねえ。
私はなにしろ全集を持ってる勝ち組なので、1886年版と最終稿を比べて、ああここを足してここを引いたんだなっていう味わい方ができます。幸せ。
以上が作者の生前に発表されたものであり、未発表のものは以下の通りです。
『街道筋』(1885)(同全集14巻)
舞台は飲み屋を兼ねた木賃宿。訪ねてくるのんべえやら悪党やらをいなす主人。ふとした偶然の重なりから、飲んだくれている男が、かつての地主階級で高貴な暮らしをし、女で身を滅ぼしたことが明らかになり……という話。「チェーホフというよりゴーリキーっぽい設定だな」って思いました。木賃宿の、どいつもこいつもろくでなしみたいな感じ、すごくゴーリキーの『どん底』っぽいです(ゴーリキーはチェーホフとも交流のあった作家・劇作家の後輩で、帝政ロシアというよりはソ連の時代を生き抜きました。彼についてもどこかで書きたいなあ)。
なぜこれが未発表かというと、検閲によって「陰鬱で不潔」という理由で発禁に処されたからです。登場人物ではメリックという悪党がほんとにやなやつなんですけどセリフ含めて江戸っ子みたいでかっこいいです。チェーホフはまじでいろんな人を書けます。地主貴族(『桜の園』とか)も、都会の官吏(『心ならずも悲劇の主に』とか)も教授(『退屈な話』とか)も医者(『敵』とか)も、農民(『谷間』のすばらしさ!)もきっちり描写できますが、ここに出てくる酔っ払いたちを見ると、ほんとに誰でも書けるんだなあと思います。やはり取材とフィールドワークの賜物でしょうか。
『タチヤーナ・レーピナ』(1889)(同全集14巻)
結婚式の最中。長いなあとかタバコ吸いたいなあとか勝手なことを言っていた人々だったが、ふいに、「呻き声」が聞こえることに気が付き、騒然となる。もしやレーピナではないか……?
こんな貴重なものが読めるなんてほんと全集があってよかった!なぜ貴重かというと、これは『タチヤーナ・レーピナ』というスヴォーリンの戯曲のいわば二次創作のエピローグなんですね。チェーホフのよき理解者であり、「新時代」紙の編集長でもあるスヴォーリンがこの同タイトルの芝居を上演した際に、「たいそう安い、役にもたたないプレゼントをします。しかしこれは、わたしだけしか贈れぬ品です」と手紙に書いてこの戯曲を贈っています。スヴォーリンはこのプレゼントを、自分の分とチェーホフの分の二部だけ刷ったのでした。スヴォーリンとの手紙のやりとりは、作家と編集という立場にとどまらないものがあり、チェーホフはスヴォーリンあての手紙のなかで、作品の構想だとか、自分の芝居に関しての役者への感想だとかを書き連ねています。このあたたかい友情は、のちにあの有名なドレフュス事件に関しての意見の相違により、すっかりひびが入る運命にあります。
『公判の前夜』(1890年代中頃?)(同全集14巻)
これ未完ですので、必ずしも1幕だったかどうかはわかりません。1886年に書かれた同名の短編の改作なので、そちらを参照すればオチまで知ることができます。重婚の罪で訴えられた男が、公判を明日に控えて宿屋に泊ってるんですが、どうしても誘惑に勝てずにたまたま同じ宿に宿泊してた女性をナンパ。途中で女性の夫が一緒に泊っているもののあんまり気にせず口説いちゃう。その夫こそが明日男を裁くことになる判事だとも知らずに…。
滑稽な、ちょっとつやっぽくもある話です。
以上に紹介した作品はのいずれも愉快なものです。四大戯曲はチェーホフ後期、それこそ死の直前くらいに書かれ、脂の乗り切った素晴らしい筆使いなんですけど、初期のものは初期のもので明るくて私は好きです。チェーホフは裕福でない家に生まれ、「アントーシャ・チェーホンテ」というペンネームでユーモア雑誌にほんの数ページずつの短編を書きまくり、医学校の学費を稼いでいたのです。たとえば前述の『公判の前夜』もチェーホンテの名前で書かれたもので、ほんの短い作品なんですけど、それでも「長すぎる」という理由で雑誌掲載がかなわなかったんです。
私が全集を手に入れたいきさつも、この大量の短編にあります。
高校3年間、学校の図書室のロシアの棚に張り付いて読み尽くしチャレンジをしていたわけですが、チェーホンテの超短編はほんとに数分で読めるので、授業と授業の10分の休憩にわざわざ図書館まで行き、一編読んではまた教室に戻るというのを繰り返していました。
卒業時、図書の先生から、「笠浦さんも卒業するし、ロシアの棚は縮小します」という宣言をされ、ゴーリキーとトルストイの全集についてはまんまともらい受けたのです(重すぎてほとんど実家に置いてきてしまいましたが)。その時チェーホフの全集については苦渋の決断で図書室に置いてきたのです。これからやってくる1年生がそれを手に取って読むようにと……。大好きなチェーホフの全集はいつか大人になったら定価で買ってやるぜと思っていたのでした。
時は流れ、大人にはなりましたが、私は貧しく家も狭く、とても全集なんぞに手を出せる身分ではありませんでした。ところが、あの高校生の日に、ほんの少しの休み時間を使って読んだチェーホフの短編が、繰り返し思い出されるようになりました。「父と子がいて……お母さんはもういなくて……お父さんがなにかで子供を叱っている…?」みたいなあいまいな記憶で、タイトルはどうしても思い出せません。そこで定価で買うという志を捨て、中古販売に手を出し、1巻からの大捜索の結果、どうやら目当ての短編は6巻収録の『家で』であると特定したのでした。
かくして全集と暮らすようになって気が付いたのは、ここまで一人の作家の作品が集結し、生活空間にそこそこの体積を占有されると、全集に人格のようなものを感じるということです。
このように外出もままならず人との会話もできない状況下で、特に公演や稽古ができないというストレスの中で、孤独に押しつぶされそうなときもありますが、私は一人暮らしではなく、全集との二人暮らしであると考えれば心も和みます。
つまり、私が読んでくださっているみなさんに言いたいことは、精神の安寧のために全集を買えばいいということです。別にチェーホフでなくて構わないのですが、誰かの書いたものをすべて読むというのはかなり骨の折れることであり、こういう機会にしかできないことなのかもしれません。
最後にとってつけたようにあれですが、どうぞ引き続きクラウドファンディングをよろしくお願いいたします。

 FUNDED
FUNDED