「キッズデザイン賞をいただくまでの物語」
vol. 3 2025-08-14 0
パブリコに携わるひとびとの言葉もリレー形式で紹介していく”アップデート”。今回は、パブリコの設計を手掛ける「tantable」の丹治健太さんによるコラムを2回に分けてお送りします。
ーーー
「キッズデザイン賞をいただくまでの物語」
2024年、publicoはキッズデザイン賞・審査員特別賞を受賞しました。
でも、そのはじまりは、決して華やかなものではありません。
3年前、「あの子もこの子もみんなの子」という合言葉から始まったのは、
ちょっと手づくり感あふれる挑戦でした。
写真右:丹治さん、写真中央:石山(amigo理事長)、写真左:壬生(パブリコマネージャー)
はじまりは、ただの“願い”から
私たちが思い描いたのは、
産前産後のママやパパがふらっと立ち寄れて、
親子同士が出会っておしゃべりできて、
子どもたちが自由に走り回れる場所。
公共施設のように堅苦しくなく、カフェのように静かにしなければいけないわけでもない。
そんな空間や仕組みは、既存の街にはなかなかありません。
予算は、もちろんあまりない。
でも代わりにあったのは、
「誰もが自分の居場所だと思える空間をつくりたい!」という強い気持ちだけでした。
セルフビルドという選択
「お金がないからセルフビルド」ではなく、
「セルフビルドだからこそできる空間をつくろう!」と声をかけました。
集まったのは、世田谷区の大学生、近所の物知りお兄さん、なんでも作れるおじいちゃん…。amigoのおでかけひろばを利用しているお母さんお父さん。。。
皆、建築の素人ながら、打ち合わせを重ね、熱く語り合いました。
材料は、以前つながりのあった南会津の製材所から、杉の柱を原価で譲ってもらい運び込みました。
壁は床と天井の鉄レールに杉の柱を挟み込むだけ。
床はその柱材をただ並べるだけ。特殊な道具も金物も不要なので、子どもでも仕組みがわかります。
床はゴツゴツ、高さもバラバラ。
でもその“ちょっと不揃い”が、子どもには探検のようで楽しく、
親には懐かしい家のように落ち着ける。
木の香りが満ちて、公共施設にはない手ざわりとぬくもりがありました。
みんなでつくった、みんなの場所
工事の日には、地域の人たちや国士舘大学の学生たちが集まり、
スケッチを描き、壁を立て、笑いながら木を運びました。
余った木材で学生たちが即興でつくった本棚は、
今も現役で活躍する立派な力作です。
こうして完成したpublicoは、
「完成して終わり」ではなく、「使いながら育つ」建築になりました。
そして受賞
審査員の方からは、こんな言葉をいただきました。
「これからの建築は、与えられた価値を形にするだけではなく、
自らが欲しい空間をつくり、使い、更新していく“関わり方のデザイン”が重要になる。
publico
は、そのモデルとなる空間づくりを体現している。」
つまり、この場所はただの建物ではなく、
人と人の関わりそのものをデザインした空間なのです。
そして、次の物語へ
今、私たちはこのpublicoに、
銅板ホットケーキブースという新しい物語を加えようとしています。
焼きたての甘い香りと、人が集まる屋台のような温かさ。
この続きはまた次回。
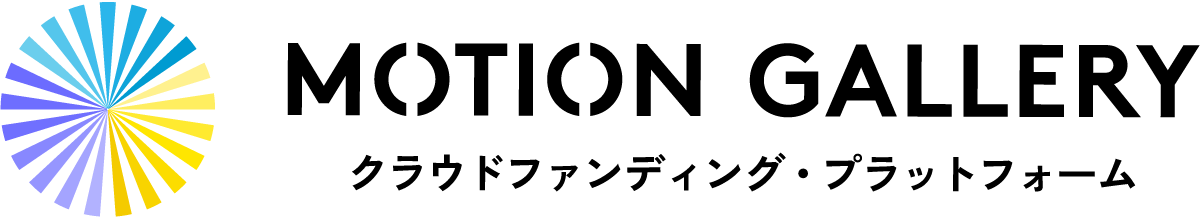
 FUNDED
FUNDED











