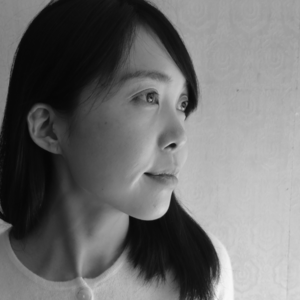教会ー境界 ①
vol. 21 2019-12-13 0
教会
ルーマニアには、数多くの教会があります。
街の中、歩いているとすぐに見つかる、というくらいたくさん。
・
わたしはなぜか小さいころから「教会」という存在がすきでした。
初めて訪れたのがいつだったか、記憶していませんが、
教会にいるとどんな気持ちになっていたかは感覚に新鮮な記憶のまま残っています。
「私が求めるものが全てある、懐かしい場所。」
全然しらないはずの教会は、その内部にはいると、
どの教会であっても「懐かしい」と感じてしまう。
そこに子供の私はなんの不思議も感じることはなく、ただ
「きっとどこか本の中で出会ってるんだろう」くらいに考えていました。
・
その記憶が教会を見るたび、思い出されるのです。
わたしはルーマニア、とくにブカレストに滞在しているときにはいろんな教会へ足を運びました。
・
・
・
扉・窓ーこことあそこのぼんやりとした境界。
子供のころ、
わたしはファンタジー小説がすきでよく読んでいて、
わたしはハードカバーの本が好きで、重たい本(実際の重さが)ほど、
その中身の世界への期待も高まりました。
分厚いハードカバーの本の表紙を開く時の期待感、高揚感。
いまから別の世界へいくのだと胸が高鳴ったのを覚えています。
・
・
・
大人になった私もまだ、ハードカバーの本がすきです。
いまでも子供のころ同様の感覚は持っていて。
ルーマニアで教会の扉に触れる度、
ハードカバーの本の表紙を開くときと、教会の重たい扉を開くのは似ているかもしれない
と感じました。
・
・
教会の入り口。重たい大きな、古い扉の軋む音をききながらゆっくり手でおしていく。
その動作は「これから外界とは違う場所へ行く」儀式のようにも感じました。
たった、扉一枚。
動かすことの出来る壁。そのむこうには外界とは違う空気が満ちているのだろう。
動作と同じ速度で、わたしは自分の中の意識の立ち位置がじゅわっと変わるのを感じました。
・
・
扉をひらく動作が、意識の壁をパイプに変える。
・
・
・
・
アイコン
ところで、
「教会」というのは遠目にみていても、すぐにわかります。
シンボルとして必ず「十字架」が、建物の一番高い位置に掲げられているから。
クルジュでは丘の上、町から遠く離れた場所からでも、町の中心にあるそれがわかりました。
建物の様式は様々だったけれどそのアイコンだけは、どこも同じ。
(なかにロシア様式のがあって、その屋根のかたちは独特だった。)
「十字架」というアイコンがつくことで、
どんな建物であっても人々は「教会」だと気づくことが出来る。
・
キリスト教徒のひとたちは、
「教会があそこにあるのだ」と思うと、ほっとするのでしょうか。
心安らぐ場所はいつでも「あそこ」にあるのだと。
たとえ自分の居場所が、家の中にも社会にも、どこにも見出せなくても。
教会は、誰にでも開かれていて、いいも悪いもさらけ出せる場所なのだろうか。
(「懺悔の部屋」、「告解の部屋」があるというところもなにか、、、)
救いがある場所。
・
「それってどこか、「アート」と呼ばれるものの存在にも似ているかもしれない」
と、丘の上から教会をみつけたときに私はふと、思ったのでした。
・
・
・
わからないものー言葉でわかる、ものでわかる。
教会の外見が様々であったのと同様に、
教会の扉を開けたその内側も、構造はさまざまでした。
祭壇につづく通路がとてもながくてその両脇に長いベンチがずらりと並んでいて、柱も、壁面の装飾も、天上や窓にはステンドグラスがはめこまれているような豪華なところもあれば、
とても小さい、日本の小学校の教室のような質素な教会も。
(カトリックとプロテスタントの違いだろうかとも思ったけれど。そこまでは立ち入って聴くことが出来なかった)
でもどんなにちいさな空間でも、大きな空間でも、同じなのは、壁面や、天井、もしくは絵、彫像などで、聖書の場面を描いていることでした。
何も飾られていないたただの「箱」状の教会というのは、わたしが訪れた中にはひとつもありませんでした。
・
「はじめに言葉ありき」
キリストによる世界は、言葉からはじまる。
神さまの言葉があって、世界が創造される。
・
かつては文字を読めない人たちもたくさんいて、もしくは違う言語を話す共同体もきっとあって、それであってもキリスト教を布教していく必要があって、だから、そのための道具として絵や物を使った。
本当は、かたちにすることはよくないことだったのだろうけれど。
それほどキリスト教を伝えることに対して、信者のひとたちは使命感もあったのだろうし、
いいものと純粋に信じているから良かれと思って自ずとそうしたのだろうし。
政治的な色合いが濃いことも、あったかもしれない。
(私は昔の人たちの気持ちはどうだったのだろうと思いをはるか遠くに馳せるのが好き。)
ともかく、文字の読めないそのひとたちにもキリストの教えを何とか伝えようと、絵や、彫刻などでその教えの大切な場面を表現したのだと、教科書的な知識として記憶しています。
それが「キリスト教美術」とカテゴライズされているもの。
・
でも、「キリスト教美術」といわれるそれが発明された、その当時。
たとえ文字を読めない人々も、共通言語の領域でなら、日常会話はできたはずで。
口頭だけでは足りなかったということなのだろうな。
きっと、教えを具現化したそのいろいろな「物(今は美術品)」を窓のようにして、誰かから「これは〇〇の節の〇〇の場面で」などという説明を聞きつつ、
キリストが見て感じていたであろう世界を想像したのだろうなあ。
・
と、キリスト教が布教されていた当時の、「文字が読めない人々」のことをわたしも想像してみました。
・
其処で、わたしはふと思ったのです。
「語られる言葉がなければ、聖書をしらなければ、目の前にあるその絵や、彫刻は、
文字をよまずキリスト教をしらないひとびとには全く意味をなさないものだったのだろうか。」
「それとも、なにもわからなくても、目の前に在るその表現物を見たり触れることだけで、人々は満たされたのだろうか。そこから、それがなんなのかと惹かれたひともいたのだろうか。それも信仰になったのだろうか。」
「もしくは全くキリスト教の文脈とは関係なかったけれど、ちょうど良く見立てられたなにかが、伝えるための道具になることも、あったのだろうか。そんなことをしたら罪になるのだろうか。」
・
なぜこんなことを思いついたのかというと。
教会の建物に描かれた絵、もしくは壁に飾られている絵も彫像も、時代の違いによってその描かれ方、作られ方、顔の感じなどは違うし、キリスト教についても、聖書の中身についても、ほとんど何も知らないわたしには正直、どの節のどの場面かというのは、正直全くわかりませんでした。
それでも、わからないなりにわたしは何かを確かに感じ取っていて、それはそれは厳かな気持ちになったのでした。
清々しくて、重苦しい気持ちが解きほぐされていくような心地にもなりました。
・
「わからない。」とは、言葉で説明はできない、ということです。
「目の前に在るものの存在意義が何なのか、わたしは知らない。」ということです。
・
「わからないのに、こうも厳かな気持ちになるのはなぜなのだろう。」
「わからないものに対して、こんなに心地よく感じていられるのはなぜなのだろう」
と不思議に思いました。
同時に、「わからないことに対してどうしてこうも私の心が影響を受けるのか」
ということに改めて気づいたわたしは、「わからないまま影響をうけている自分」に戸惑いました。
それが、自然の中でのことでも、美術館のなかのことでもなく、教会のなかでの出来事だったから余計に。
子供のころ教会を訪れたときには至らなかった疑問が、大人になって、ルーマニアに来て、
ようやく浮かんできました。
あのころはただ、その空間の清らかさだとか、装飾の美しさにうっとりして、「ファンタジー小説」のなかにいるような気持ちでいただけだったから…。
(気づかずに感じ入るばかりだったあの頃がうらやましい)
いまだから浮かんだ疑問。
きっとそこには意味がある。
・
でも、残念なことに、疑問はすぐには解決しなさそうでした。
・
日本に居る今も、まだその「?」の周辺を、くるくると衛星のように回っているだけ。
実は、その答えになるものをなんとかここに書けるのではないかと、この数か月書いては消してを繰り返していました。
でも、文字を連ねていけばいくほど、その文字が震え始めてぐちゃぐちゃになって、
まるでテレビ画面の「砂嵐」を失望の眼差しで見つめているような心地。
解決はいつになるのやらと途方にくれつつ、それでもわかるところまでは書いてみよう、
と。今私は画面の前でキーボードを打っている、という次第です。
・
けれど。
もしそこに自分の考えをはっきりともつことができたのなら、
わたしはこの先ずっと、アート世界で重要視されつづけている「コンセプト」というものに思い悩むことも、弄ばれることも、其処に対する不必要な劣等感を感じることも葛藤も、なくなるのだろうなと、
それだけは直観していて、だから、できるだけ早くそれを見つけたいというのは、正直な気持ちです。
・
もし、これを読む人の中に
「わたしわかります」
と思う方がいたとしても、どうか私にはその答え、内緒にしていてくださいね〇
・
・
・
・
境界をもたないルーマニア人の友人
「ここがルーマニアで訪れる最後の教会だろう」
・
友人と歩いていたわたしは、遠目にまた「十字架」をみつけて、
友人に「あそこへ行きたい」と伝えました。
実は、ルーマニアで行った教会は、ほぼ全てこの「友人」と一緒でした。
・
彼女はルーマニアで生まれ育った人。今はフランスで建築デザインの仕事をしていて、
今回わたしの渡航時期にたまたまルーマニアで仕事があるということで、一緒に街をめぐることが出来たのです。
彼女はとてもおしゃべりずきで、彼女の辞書に「沈黙」という言葉はのっていないのかもしれないと思うほど。
彼女は絵に描いたような「フレンドリー」なひとで、だれにも「フランク」で、それに思いやりと愛に満ちた女性。
行く先だけでなく、道中で出会った人とー例えば横断歩道の待ち時間隣に並んだ人とですら、会話ができてしまうのだから、すごい。なにがすごいって、彼女が一方的に話しているわけではなく、みんな彼女にはすぐに心開いてしまう。
彼女にかかれば全員「友達」。
と、しばらくそう思っていたけれど、
なにもそれは彼女の特技というわけではなくて、ルーマニアの人は人懐こく精神的距離の近いひとたちなのだということが、彼女と街を歩いているうちに次第に理解することができました。
ルーマニアの人々は、誰かの質問が耳に入れば、我先にと答えてくれるし、初めての相手に自分の身の上話まで暴露してしまう。「プライベート」というのはこの国ではどこからどこまでなのか、と不思議に思ってしまうほどです。
それにしたって、わたしの隣を歩く彼女は、自他の境界がまるでないようなひとだとわたしは感じていました。
彼女が「自分の境界線」をつくらないということよりも、彼女が話せば、目の前にいる人は彼女の世界に一瞬でひきこまれてしまって、彼女の世界の住人になってしまうというところで。
彼女はだれにでも、両手を広げて「どうぞどうぞ」と招き入れるのです。
彼女の大げさなくらいの表情の変化や、抑揚豊かな話し方。
ぐるりと目を回したり変な顔をしたり、身振り手振りはもちろんのこと、
自分が経験した場面を、自分の立ち位置を変えながら、全身で表現するのだから。
彼女がそれを意図しているわけではないのに、彼女のために必要な空間は次第に広がって、彼女のおかげで歩道が「劇場化」していく。
二日間彼女といる間に、ルーマニアのひとたちは、そういう話し方を好んでするというのも、徐々にわかっていったけれど。
だとしても、わたしの隣で活き活きと「表現」しつづける彼女はルーマニア人のなかでも飛びぬけて「ルーマニア人」でした。
どこへ行っても彼女が彼女を全力で惜しみなく他人に差し出す姿を見ていて、
彼女のことを誇らしく感じつつ、もしかしてこれが日本なら恥ずかしかったかもしれないと思うとこの土地で彼女と歩ける幸運を噛みしめずにはいられませんでした。
・
・
そんな彼女も、教会に入るときには、その素晴らしい演技力を抑えて、控えめな声と表情になるか、ひたすらその場に感じ入っていました。
さっきまであんなに外へ向けてエネルギーを発散していた(ように見えた)彼女が、そのエネルギーを丁寧に折りたたんで自分の中にしまっているようで。
それを見ていても、教会という場所のもつ力の不思議さを思わずにはいられませんでした。
・
・

 FUNDED
FUNDED