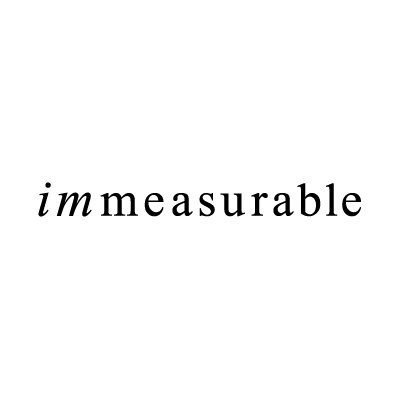クラウドファンディング24日目!まずは万博を知るところから
vol. 4 2025-04-09 0
前回に引き続き、編集メンバーのえじりです!
いよいよ今週末から大阪・関西万博が開催されますね。私たち編集メンバーも、本誌に掲載するインタビューを行うため、今週末に大阪を訪れます。また、5月には執筆メンバーも含めて、実際に万博を訪れる予定です。
最近は、万博を解体していくための最初のステップとして、万博について勉強するところからはじめています。批判するにも肯定するにも、まずは相手を知るところから。
今回の記事では、万博に関する面白かった本を紹介していきます。ちなみに、本誌でも「万博を解体するためのブックリスト(仮)」のページをつくろうと思っていますので、どんなZINEができるのだろうかと想像しながら読んでいただけると嬉しいです!
1. 万博に関わる立場から
①『やぶれかぶれ青春期—大阪万博奮闘記』(小松左京、新潮社、2018年)
SF作家・小松左京が、批評的な意味を込めて「万国博を考える会」という自主勉強会をやっていたら、1970年の大阪万博の関係者に声をかけられ、ブレーンとして関わるようになっていく、というフィクションみたいな出来事を振り返る奮闘記。
②「年代記的ノート」『空間へ』(磯崎新、河出書房新社、2017年)
1970年の大阪万博で《お祭り広場》を設計した建築家・磯崎新による「年代記的ノート」。複雑な思いを抱えて大阪万博に関わった一建築家の苦悩が書かれている。
2. 万博に反対する立場から
③『われわれとって万博とはなにか』(針生一郎[編]、田畑書店、1969年)
1970年の反博運動を先導した美術評論家・針生一郎を中心として、多木浩二、宮内嘉久、粟津潔、大岡信などの錚々たる顔ぶれが、建築、美術、デザインなど分野横断的に万博を批評する。
④『肉体のアナーキズム—1960年代・日本美術におけるパフォーマンスの地下水脈』(黒ダライ児、グラムブックス、2010年)
1960年代に胎動した「反芸術」的なパフォーマンスを総覧できる一冊。万博破壊共闘派など直接的な行動で万博に反対した人たちが紹介されている。当時の様々な運動の中で反博運動を捉えることができる。
3. 万博の建築・美術・デザイン
⑤『戦争と万博』(椹木野衣、美術出版社、2005年)
「万博芸術=もうひとつの戦争美術」という見立てのもと、1970年前後の前衛的な芸術運動が万博という国家的なプロジェクトに取り込まれていく様子が描かれている。当時の重要な人物や出来事がコンパクトに分かる。
⑥『10+1』No.36「特集=万博の遠近法」(INAX出版、2004年)
椹木野衣、五十嵐太郎、小田マサノリが聞き手となり、黒川紀章や磯崎新へのインタビューを通して1970年の大阪万博を振り返るとともに、建築・美術・デザインの観点から「万博」を問い直す。
⑦『オリンピックと万博—巨大イベントのデザイン史』(暮沢剛巳、筑摩書房、2018年)
1964年の東京オリンピックと1970年の大阪万博を題材として、デザインの黎明から政治との関係まで、戦後日本のデザイン史がコンパクトにまとまっている。国家的なプロジェクトと表現の関係を考えるうえでも良い一冊。
4. 万博の政治学
⑧『博覧会の政治学—まなざしの近代』(吉見俊哉、中央公論新社、1992年)
博覧会の歴史を振り返り、大衆の欲望と国家の権力が絡み合って博覧会を生み出していくプロセスや、近代社会の「まなざし」のメカニズムを描き出す。
⑨『万博幻想—戦後政治の呪縛』(吉見俊哉、筑摩書房、2005年)
社会学者・吉見俊哉が愛知万博に関わった経験も踏まえて、大阪万博、沖縄海洋博、つくば科学博、愛知万博という戦後日本の万博の背景にある政治的な力学に迫る。
* * *
といった感じで万博について一から勉強しているのですが、今後も関連書が出版されたらチェックしていきたいと思います。
引き続きプロジェクトをご支援・シェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします!
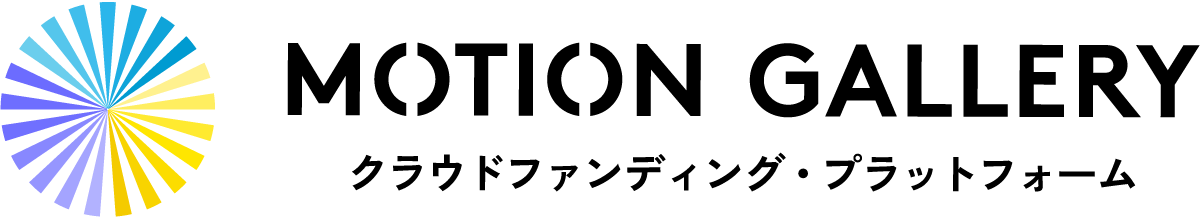
 FUNDED
FUNDED