自主上映運動40年、そしてこれから
vol. 1 2025-02-22 0
コレクターの皆様
『よみがえる声』劇場公開のためのクラウドファンディングに応援をいただき心より感謝申し上げます。
初日から多くの方からご支援をいただき現在、26人の方から439,000円のファンディングが集まりました。『よみがえる声』は夏の公開を目指して、日々、配給のための準備作業を進めております。
朴壽南(パク・スナム)が作家からドキュメンタリー映画制作へ転身したのは今から40年前、1985年、50歳の時でした。
画像は当時、第1作目の『もうひとつのヒロシマ』制作のために広島の在日朝鮮人被爆者を取材、撮影している場面です。
左がパク・スナム。右は、広島の江波町(現中区)の軍需工場で26歳の時、被爆した姜文煕(カン・ムニ)さんのご夫人。姜文煕さんが経営していた焼肉屋で取材をしているところで、16ミリ・フィルムをデジタル復元して初めてよみがえった映像です。(姜文煕さんは2014年逝去されました。)
自主上映運動40年
翌1986年、在日、在韓の被爆者16名の証言を紡いだ58分の『もうひとつのヒロシマ−アリランのうた』を自主制作で完成させ、草の根の市民の上映によって全国300カ所で上映運動が広がりました。母に聞くと、劇場で公開するという発想は全くなかったそうです。
娘の私(朴麻衣)は当時まだ高校卒業し大学に進学した頃ですが、配給会社も何もなく母は自主上映会会場へ走り回り、志をともにするボランティアの方々の傍で、私は手書きのニュースを母と一緒に作ったり、あちこちの集会によくチラシを配りに行きました。
もちろん、パソコンもインターネットもない時代です。
ガリ版刷り「もうひとつのヒロシマ」上映運動ニュース1号

「日本による植民地によって被爆した朝鮮人たちの二重の苦しみ、証言を多くの人へ知らせたい」と多くの人々が自分の地域で自主上映をたちあげていった情熱を今も昨日のように思い出します。
撮影も16ミリフィルムから今やデジタルで誰でもが撮影できる時代に変遷し、宣伝方法もネットやSNSが中心となり、目まぐるしく変わりました。ただ、「映画は作っただけでは完成したとは言えない。観てもらってこそ本当に完成したと言える」という、朴壽南監督の上映運動の姿勢は40年間、変わりません。
夏の公開を目指して、必要な宣伝素材を十分に用意して『よみがえる声』という映画の存在を多くの方に知ってもらえるよう努力したいと思います。応援スタッフが足を棒にしてクラウドファンディングのチラシを配りに歩き回っています。
SNS、口コミ、チラシ配り、どんな方法でも良いのでこれからも応援をよろしくお願い致します。最後まで読んでいいただきありがとうございました。
まだ寒い日が続きますのでどうぞ皆様もお身体ご自愛ください。
『よみがえる声』上映委員会 朴麻衣
- 前の記事へ
- 次の記事へ
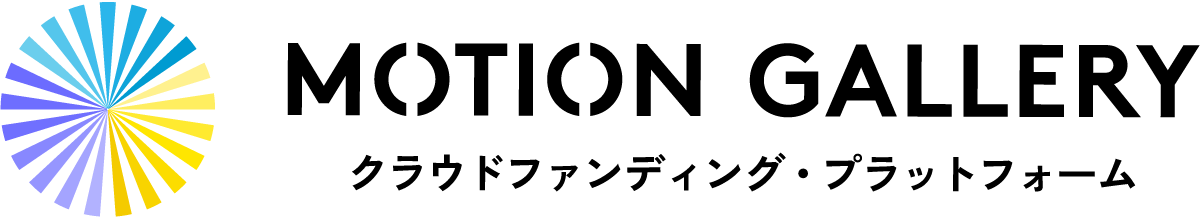
 FUNDED
FUNDED

