被害者も加害者も、私たちの社会の一員だ──朱喜哲さんからの応援コメント
vol. 33 2025-05-14 0

朱喜哲 哲学者
<プロフィール>
哲学者。1985年大阪府生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。大阪大学社会技術共創研究センター招へい准教授ほか。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。著書に『人類の会話のための哲学』(よはく舎)、『〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす』(太郎次郎社エディタス)、『バザールとクラブ』(よはく舎)、『100分de名著 ローティ『偶然性・アイロニー・連帯』』(NHK出版)。共著に『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』(さくら舎)、『世界最先端の研究が教える すごい哲学』『在野研究ビギナーズ』、『信頼を考える』(勁草書房)など。共訳に『プラグマティズムはどこから来て、どこへ行くのか』(ブランダム著、勁草書房)などがある。
<応援コメント>
私たちの社会には、刑務所がある。
それはしかし、私たちの社会の一部としてある。
刑務所に入っているひとは、手続上なんらかの犯罪を犯したと認定されて(ただし誤認を含みうる)、そこにいる。そこは物理的にも心理的にも、高い「壁」で外部から遮断され、自由な往来ができない。そこにいることは自由を大幅に制限されることであり、だからそれは「刑罰」になり、そこに入りたくないと皆が思うことが犯罪の抑止になりうる。そう言われる。
こうした、「犯罪」に対して「刑罰」を与えることを類型とする伝統的な「司法」(“Justice”だから「正義」とも訳しうる)の考え方を、「応報的な司法(正義)」という。「目には目を、歯には歯を」というやつだ。
しかし、1970年代以降、こうした司法(正義)観とはまたちがう考え方が、広まってきている。それは「修復的な司法(正義)」と呼ばれる。修復的司法は、「処罰」ではなくて被害当事者や加害当事者たち同士、その周囲、さらにコミュニティを巻き込んで関係性を「修復」することを重視する。これはもちろん、「刑罰」をなくすことを意味するわけではない。しかし、その意味合いは変わってくる。「罰する」ことではなく、「修復する」ことに力点が置かれる。
私は、最初この理念に触れたとき、どうしても感情的な反発を覚えてしまった。なぜ、被害者が加害者を「許し」たりしなくてはならないんだろう、と。でも、それは力点がちがっていた。これは、むしろ被害者(や遺族など)にずっと「被害者」としての在り方を強いることの残酷さを直視し、「なにもなかった」ことには戻らないけれど、そうでなくたってまた違う形での「日常」に戻っていいんだ、という「被害者」像の更新こそが、その眼目であったのだと思う。そして、もっとずっとむずかしいけれど「加害者」像も、また。
被害者も、そして加害者も、私たちの社会の一員だ。「加害」も「被害」も(それが事実だとして)ひとつの側面でしかない。私たちの誰もがそうであるように。
「刑務所アート展」について、かつて修復的司法に触れたときの私に似た「反発」を覚える人がいるとして、だからそれはある意味で「自然な」応報感情なのだけど、いまそれを乗り越えようという動きがあることも知ってほしい。そして、たぶんそれはこの展示を見ることで体感されることなのだと思う。
***
朱喜哲さん、応援コメントありがとうございます。
5月26日まで、第3回「刑務所アート展」展示会の開催資金を集めるため、目標250万円のクラウドファンディングを実施しています。ぜひ、プロジェクトページをご覧になり、ご支援いただければ幸いです。
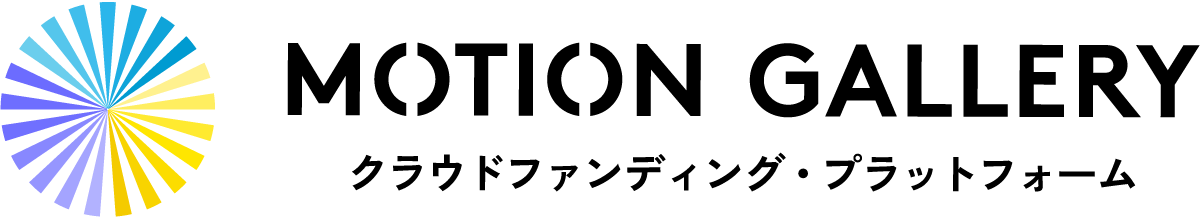
 FUNDED
FUNDED