映像祭、無事に終了しました。そして、これから
vol. 5 2025-04-17 0
「森と人々、美しき暮らしの継承へ」
映像祭ディレクターの木川剛志です。
第7回日本国際観光映像祭が無事に終わりました。
そして、支援者のおかげもあり、4本の観光映像を作ることもできました。
与論島を舞台にした映像が2本、
和歌山県田辺市龍神村の映像が1本、
そして開催地である岡山県真庭市の映像が1本。
そのプレミア上映の模様を紹介します。
上映順に4本の映像を紹介していきます。
「ユンヌフトゥバ」 監督:土屋哲彦
初めに紹介するのは、土屋哲彦監督の作品です。土屋監督は商業映像の世界で、CMディレクターとして活躍されている方です。また、映画作品においても、長編映画としては「闇金ドッグス」シリーズでよく知られていますし、短編映画では「追憶ダンス」「惡党と物書き」「再演」といった作品が全国の映画祭で高く評価されてきました。それだけではなく、プラネタリウムのような全天周映像の施設で、そこに投影する映画も先駆的に作られてきた方です。
「ユンヌフトゥバ(与論語)で島の人に語ってもらう。」
そんな土屋監督が注目したのは、与論島の方言でした。現地では「島言葉」と呼ばれる、昔から使われてきたローカルな言葉(ユンヌフトゥバ)で島民たちが語る。それも島の魅力、好きな場所や思い出といった、彼らにとって大切な何かを語る、という企画となりました。
冒頭、地元の少女から伝えられるところから、すでにユンヌフトゥバ。聞いてもらえば、わかると思いますが、本当に優しい言葉なのです。その背景で見られる美しい風景、そして地元で歌い継がれてきた音楽。実際のところ、ユンヌフトゥバは若い世代はあまり語ることができなくなった言葉です。それをしっかりと継いでいこうという試みも島ではされていると聞きます。その意味では、この作品は、アーカイブとしても大切な映像となったのではないでしょうか?
実際、土屋監督は、島の人たちと語り、そして飲み(笑)、その空気が映像にも載っていました。訪れる人を温かい気持ちにさせる島、がそこにはありました。(* 与論には、与論献奉というおそろ、、、素晴らしい儀式があります!)
観光映像祭ではこのような議論が起こることがあります。それは、地元の人々は観光動機につながるのか?という議論です。普通に観光客で観光地を訪れると、地元住民と触れ合う機会はそれほど多くはありません。なぜならば、多くの観光地では、住民の場所と、観光客の場所、がわかれているからです。しかし、だからといって、地元の住民の生活は観光に関係ないのでしょうか?観光は場所を訪れます、その場所の源泉は住民なのです。
この映像は言語、ユンヌフトゥバ、が観光客と住民との間の境のようなものとして現れています。島の言語は島民のものであり、観光客のものではありません。しかし、そのわからない言葉を聞くことで、観光客は何かに触れるのです。ここに観光の不思議さがあるように私には思えます。訪れるものが、決して手に入れることができないもの、しかしそれを感じることによって得られる、世界の広さと美しさの感覚。
土屋監督、素晴らしい映像ありがとうございました。
「与論水巡」 監督:村上浩康
次に紹介するのは、村上浩康監督の作品です。この名前を聞くと驚かれる方も多いでしょう。現在も大ヒットロングラン上映中の「あなたのおみとり」の監督、あの村上浩康監督に、無理を言って与論島で撮影をしてもらいました。村上監督といえば「東京干潟」を思い出される方も多いでしょう。東京の干潟で生活をする老人と心を通わせる村上監督。それは映画の上映がひと段落したあとも、続く友情のようです。村上監督には世代を超えた方々と心で語り合い、そして人々の心を開いていく才能があります。
村上監督に与論での撮影をお願いしたところ、まずは出てきた言葉が与論島の死生観について、でした。それは鋭い感覚だ、と思いました。実は木川も何度も与論島には足を運んでいるのですが、地元の方から言われることは、与論島の死生観は少し違いますよ、ということでした。それはどういうことかというと、与論島には少し前まで“洗骨”の風習がありました。そんなに詳しくないのですが、亡くなるとまずは埋葬する。そして数年後に掘り起こし、その骨を綺麗に親族で洗うのです。そして地元の方が言っていました。「亡くなった感覚はない。だって、そこにいるんだから」と。
村上監督はまずは地元の古老を紹介してほしい、ということを言われたので、与論島の生き字引となっておられる麓才良さんを紹介しました。才良さんはすごい人でして、地元でも才良さんに話を聞こうと島の人が集まると、昼前から夕方まで話が尽きないという方です。村上監督が才良さんと会うと、20分ぐらいで与論の水脈についてやろう、ということですぐに話がまとまったようです。
この映像は驚きでした。何度も与論に通った木川も、一度も見たことがない風景が続きます。映像の中では数箇所の水脈についてですが、実際には20近くの水脈を才良さんと見に行ったそうです。
英訳のために、自分の嫁に文字起こしを頼んだのですが、考古学に興味のある嫁は、あっというまに文字起こしを仕上げて送ってきました。あまりにも面白くてすぐに文字にしてしまったとのことです。
ドキュメンタリー作家の方への依頼だったので、当初の5分の尺は超えると思っていましたが、10分越えの大作です。与論島は観光映像を多く作ってきた島なので、なかなかに見たことのない映像はないのですが、この作品はまちがいなく、与論の知られざる何かを映し出した映像です。
村上監督、ありがとうございました。
「はしとはしのはなし」 監督:楠健太郎
さて、木川は和歌山大学の教員です。ところが、この日本国際観光映像祭を第7回まで開催してきましたが、一度も和歌山県を会場に開催はしていません。別に和歌山に恨みがあるわけではないんですが、偶然そういう状況になっています。しかし、少しずつそういう後ろめたさは募ってきましたので、今回の映像祭のテーマ「森と人々、美しき暮らしの継承へ」に合わせて、和歌山を舞台にファクトリーを開催しようと、いう気持ちになりました。
誰にお願いしよう?と悩んだ時に、浮かんできたのが、ファクトリーの常連、常勝の楠健太郎さんです。楠監督は、与論島の映像「日々是与論」にてファクトリーGrand Prixを取るだけでなく、国際観光映像祭でも受賞を重ねてきました。また、ファクトリー発祥の地、ポルトガルでも現地のファクトリーに秋田の若い二人と一緒に参加し、これまで日本チームが勝てなかった最強の敵、ブラジルと同点で並び、優勝するという快挙も得られています。
その意味では、楠監督は日本では数少ない、観光映像の作家なのです。そして、楠さんが向かった先は、和歌山の中でもなかなかの僻地、田辺市龍神村でした。
龍神村は、日本三大美人の湯で知られる温泉がある、風光明媚な場所です。そして、和歌山といえば南国のイメージなのですが、ここでは十分に雪が降るのです。幸いにも、楠監督が訪れた時は、十分な寒波が来ており、和歌山らしくない、美しい雪景色を撮ることができたようです。作品は、少しあまのじゃくの傾向がある彼らしく、直球ではない変化球の作品でした。
楠監督は、事前のリサーチで、吊り橋が一つの大きな観光資源となっていることを知ったそうです。そして、その吊り橋を擬人化して語らせる。どうしたらそんな素敵な発想が浮かぶのでしょうか。一度、福山で、彼と福山の牡蠣を食べながら小一時間聞いてみたい気分です。
今回、楠監督のチームは一人ではなく、コピーライターの方も巻き込んでのチーム。そして、ライターの方は声の出演までしてくださったそうです。その言葉と、声のトーンが優しく、その厳しい寒さの風景と対比的な暖かさとして、届きました。まるで温泉の湯気のような暖かさです。
実は、和歌山大学も龍神村とは付き合いが深いのですが、この村のもう一つの魅力は移住者です。温かい地元の雰囲気が多くの人を呼ぶのでしょう、そんな移住者が地域に溶け込み、クリエイティブな風土を作り出している場所なのです。この映像にも移住者の方々の出演があります。楠監督も、地元の人たちが優しかった、とおっしゃっていましたが、それもこの映像を温かいものにしているのではないか、と思います。
楠監督ありがとうございました。
「The Garden of Truth」 監督:粂田剛
最後に紹介するのが、粂田剛監督の作品です。こちらもドキュメンタリー映画好きの方々は驚かれる名前でしょう。フィリピン在住の困窮日本人を鋭く描いだ「なれのはて」の監督の粂田監督です。昨年も与論島の映像を撮っていただき、スペインの映画祭で受賞もされました。その粂田監督に向かってもらったのが今回の開催地、岡山県真庭市でした。
粂田監督は、他の作家とは違い、長く滞在されて、自分の足でかせいで映像を撮られます。地元で配布されている冊子に「真庭のひとびと」というのがあるのですが、この冊子も参考にされながら、1週間以上、真庭に滞在しての撮影でした。
真庭市というのは、かなり大きな市です。今回の映像祭の開催となった旧遷喬尋常小学校がある久世というのも昔は一つの自治体でしたし、少し北に行けば温泉地、湯原があり、その北には蒜山という避暑地もあります。ちなみに蒜山ではおいしいジンギスカンが食べれます。そんな広い市を粂田監督は縦横無尽に駆け抜けられたのでしょう。
実は粂田監督が真庭入りした初日は私も同席しました。そこで林業関係者とお話しをされて、森と生活するとはどういうことか、そのあたりを話し合う場に立ち会いました。そして生まれた映像が次のようなものでした。
なんと美しい暮らしでしょうか。また、そこには幾世代にも渉る暮らしがありました。そして、これも粂田監督が足で稼いで人々と会いながら気づいた点、森、自然と向き合う人々の手、手を通じた実感。それを粂田監督は映像にすることができたのでした。
もちろん、開催地の映像であり、テーマもあるので、そのような映像を期待していた自分もいました。粂田監督はあとでおっしゃいました。テーマがわかってて、それを避けようと思う自分がいたけど、まんまと木川さんにしてやられた感じで、映像祭のテーマの映像になっちゃったよ、と。ありがとうございます。こういう映像を私は見たかったのです。真庭の人々にも見てほしいし、さらにはここにこそ、日本の本質的な魅力があるんだ、それを多くの方に知ってほしいと思います。
粂田監督、ありがとうございました!
受賞結果と今後の展望
4本とも素晴らしい映像でした。しかし、このファクトリーはコンペ形式。審査員の投票の結果、ファクトリーのグランプリは、粂田監督の「The Garden of Truth」になりました。
 グランプリ受賞の粂田監督と審査委員長
グランプリ受賞の粂田監督と審査委員長
そして、クラファンの投票権の結果、観客賞は楠監督の「はしとはしのはなし」になりました。
 観客賞を受賞した、楠健太郎監督とそのチーム。
観客賞を受賞した、楠健太郎監督とそのチーム。
今後はこの4本を世界に紹介していきます。ただ、英訳は難しそうです><
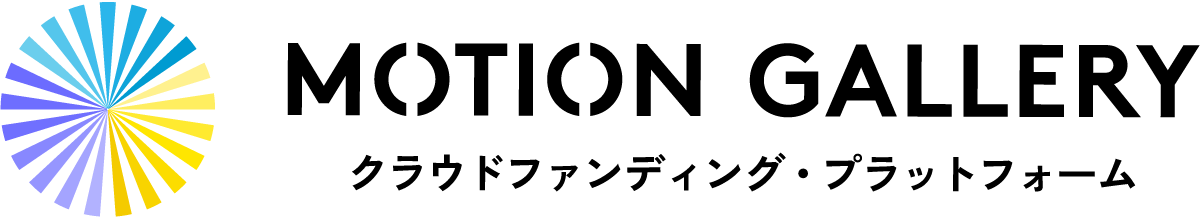
 FUNDED
FUNDED