わりとひみつ根っこのはなし
vol. 23 2025-04-12 0
「Aでもない、Bでもない、AかつBである」──テトラレンマ(四句分別)という思考法は、対立構造を超えて認識や感性を拡張する可能性を持っている。映画/映像制作においても、ジャンルや技法、主語と客体、過去と未来といった枠組みに揺さぶりをかけることで、より深い共鳴や記憶が生まれると私は考えている。
この思考と実践の原点には、「私自身がどこにも完全には属せない」という創作者としての立場がある。商業映画とアートフィルム、記録と演出、個と集団。いつもその「あいだ」に立ち、境界線の中に身を置いてきた。だからこそ、私の映像には常に「どちらでもないし、どちらでもある」視点が宿る。テトラレンマは、その実感を言葉にできるフレームであり、方法論である。
映像づくりは、私にとって「答え」を出すことではなく、「問いを手渡す」行為だ。そのためには、物語の明確なゴールではなく、観客自身のなかに生まれる余白や迷い、葛藤の“場”を用意する必要がある。形式や技法に縛られず、どれだけ“現場”が、そして“関係性”が語り出すか。テトラレンマという視点は、そのための思考のツールである。
・・・・・・
映画は、ただ物語を運ぶ道具ではない。それは、「何をどう見せるか」ではなく、「どう見ようとするか/どう関係を結ぶか」にかかっている。私が信じる創作とは、形式や手法を超えて、見る者・撮る者・映る者がともに“揺れる”場を生むこと。そして、そこにテトラレンマ的思考を重ねることで、映画はより多層的で、多義的で、観客自身の意識を拡張する触媒となる。
・・・・・・
そして、わたしは映画です/i'm a movieと言うとき。
事実、すべての認知がゆらぐ。
日の光だけが眩しい。
布村
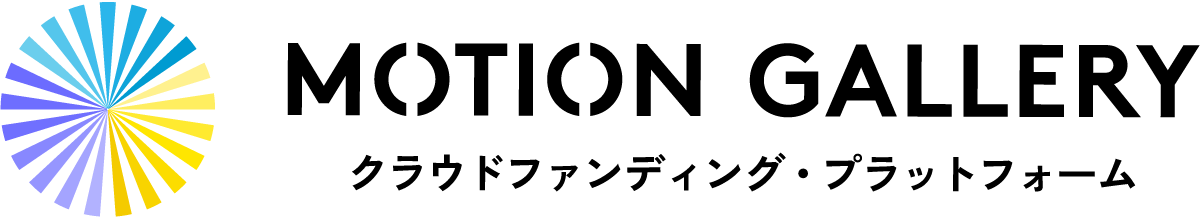
 FUNDED
FUNDED

