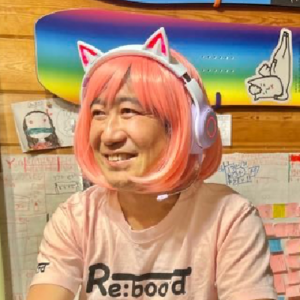おぐに黒大豆を守り続けてきたミズ子さんと黒大豆を囲む会を開催しました
vol. 29 2025-11-03 0
たくさんのご支援、誠にありがとうございます。おかげさまで目標金額を達成いたしました!皆様からのご支援でどのようなことが実現できているのか、今後もアップデートでご報告させていただきます。今回は「おぐに黒大豆を守り続けてきたミズ子さんと黒大豆を囲む会」についてのレポートです。
地面から湧き出る地熱の湯気に包まれた「わいた温泉郷」の近く、西里地区中尾集落で農業を営む財津ミズ子さんは、この集落だけで受け継がれてきた在来種「おぐに黒大豆」をお一人で守り育て続けてきました。
写真は収穫した黒大豆(右)とそれを炒ったもので淹れた黒豆茶(左)です。実はこの黒大豆は、大豆専門の研究機関でさえその存在を把握しておらず、実物を見てもらうまで「そんな種は存在するはずがない」と信じてもらえなかったほど希少なものだったそうです。それもそのはず、ミズ子さんは「在来種を守らなくては!」という使命感から守り続けてきたというよりも、むしろこの黒大豆を育て、調理したものを「美味しい!」と喜んでくれる家族やご近所さんの笑顔を見たくて、育て続けてきたのです。
今回は、リサーチャーの米津いつかが小国滞在中に毎日ミズ子さんを訪ねてリサーチを行う中で、「ここで流れる豊かな時間と空間を共有したい」と、急遽企画したイベントです。
ご自宅での開催ということもあり、小さな国に関わるメンバーや町の飲食関係者など、少人数限定での開催となりました。まずはミズ子さんとご主人の寿俊さんに、どのように日々の暮らしを営まれているのか、そして黒大豆がこれまでどのように受け継がれてきたのかについてお話を伺いました。お二人の言葉からは、自然と共に暮らす日々のリズムや、土地への深い愛情が感じられました。
その後、実際に黒大豆の畑を見学させていただきました。ミズ子さんと寿俊さんは黒大豆のほかにも、さまざまな野菜を育てていらっしゃいます。参加者からは興味津々の質問が次々と飛び出していました。黒大豆は夏の間に育ち、秋を過ぎて枯れ、カラカラになるまで畑に置いておくそうで、比較的手のかからない作物だそうです。実際にサヤから豆を取り出してみると、想像よりずっと小ぶりで、磨いた天然石のように美しく、手のひらの上で光っていました。
見学の後は、ご自宅で黒大豆を使った料理など、実に美味しそうな手料理の数々がずらりと並び、一同びっくり。しかも、料理に使われている食材のほとんどがミズ子さんの畑で育てられた野菜やお米で、味噌も黒大豆から手作りされたものでした。
豆そのものを味わってもらおうと、2日前に地元の神社の湧き水に一晩浸して、前日から当日にかけて地獄蒸しをした黒大豆は、調味料を一切使っていないにもかかわらず驚くほど味わい深く、とても美味しい。詳しい内容は、クラウドファンディングのリターン品でもある国際小国学 ZINE『小さな国 十月』で米津が記事にしてくれると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。
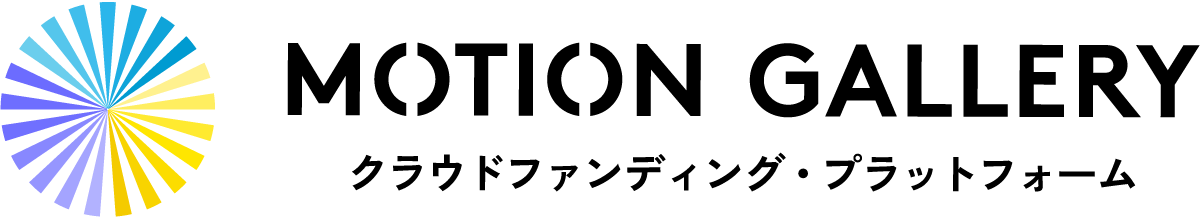
 FUNDED
FUNDED