「回復を共に考える」ことはなぜ苦しいのかー愼允翼さんからの応援コメント
vol. 54 2025-05-23 0
「第3回刑務所アート展」クラウドファンディングへ、愼允翼さんから応援コメントをいただきました。
愼允翼(しんゆに) 東京科学大学未来社会創成研究院 DLab+ 研究員
<プロフィール>
東京科学大学未来社会創成研究院 DLab+ 研究員。1996年生まれ。東京大学文学部卒、同大大学院人文社会系研究科修士課程修了。著作には次のものがある。愼允翼「第8章 なぜロマンチックは大事なのか―私の記憶をめぐって」任龍在編『肢体不自由者の自立と社会参加』、博英社、2024年、183-216頁。鈴木悠平・愼允翼『介助とヒーロー: 『ラストマンー全盲の捜査官』を2人で観る』、閒、2024年。その他メディア掲載多数
<応援コメント>
刑務所の「壁の向こうから届く声を受け止め、回復を共に考える」という本企画の目標は、率直に途方もない企てだと思う。「受け止め」ない、「考え」ないことは容易い。それは何もしなければ事足りる。ところが、敢えて「表現をひとりぼっちにしない」場所をつくろうとするならば、「考える」ことはどこまでも広がっていく。この広がりは限られた体力と知力しかない私たちを苦しめる。しかし、その苦しさをわたしは希望と呼ぶ。
「回復を共に考える」ことはなぜ苦しいのか。それは、本企画で「受け止め」られようとする「表現」が「犯罪」の後に生じるからだ。さらに、本企画は「回復」を促そうとするものでもないからだ。加害者がしてしまったこと、被害者がされてしまったことは決して無かったことにならず、誰かの心に記憶されている。このどうしようもない現実を前にしてなお生きなければならないとき、私たちは二つの道を想定することができる。第一に、既に起きた事件にいつまでも集中できない記憶の限界を認め、「回復」を「考え」始めるという開放の道。第二に、悲惨な歴史や心のありようにいつまでも向き合い続けようと、記憶の限界に挑み、消えることのない「傷害」を「考え」始めるという閉鎖の道。
重要なのは、この両方の道がはっきりと並行するのではなく、先の見えない中で交差しあっていることだ。開放と閉鎖が不規則に繰り返されることで、生きて考えることは希望を呼ぶ。閉鎖がなければ記憶や内省は生じないが、機能的に意識し続けることができないから、開放に至る。だから、その間で「考える」ことは根源的にどこまでも苦しい。それでも、加害者も被害者も第三者も、この社会で共存する人たちが「回復を共に考える」ことはできる。それは、道のりが見えない、あるいはまだ存在さえしていない暗闇の全体に一つ一つ足跡を確かめ、光を灯していくことなのだ。「受け止め」ない、「考え」ないままでは、そうした光景を見ることが永遠にできない。その虚無をわたしは絶望と呼ぶ。
本企画の途方もなさと希望とは、私たちの人生の「取り返しのつかなさ」を引き受けながら「表現」を諦めない勇気に不可欠な困難の別名である。
***
愼允翼さん、応援コメントありがとうございます。
5月26日まで、第3回「刑務所アート展」展示会の開催資金を集めるため、目標250万円のクラウドファンディングを実施しています。ぜひ、プロジェクトページをご覧になり、ご支援いただければ幸いです。
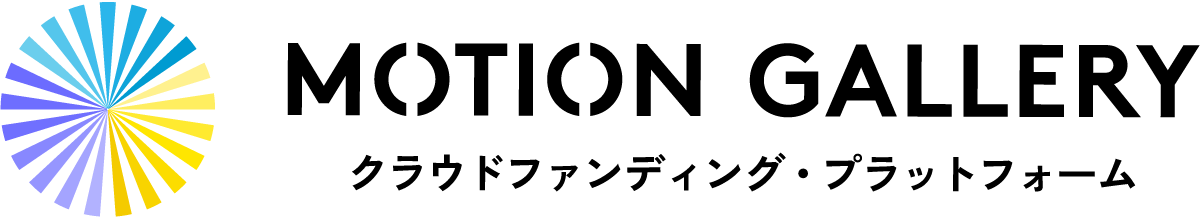
 FUNDED
FUNDED
