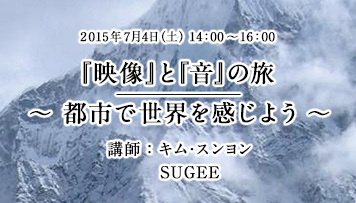日本の伝統文化である落語に縁のある映画が相次いで制作・公開されます。ひとつは、自堕落な落語家を主人公に据えた壱岐紀仁監督の「ねぼけ」、そして人気落語家、柳家喬太郎主演の吉野竜平監督の「スプリング、ハズ、カム」。二人の監督はなぜ、同時期に落語や落語家にフォーカスし、そしてなぜ、MotionGalleryでのクラウドファンディングを通じて映画を作ろうと思ったのか。両監督との鼎談のなかから探ります。
きっかけは、ポール・トーマス・アンダーソンの「マグノリア」?
大高:ちなみに、お二人が映画を撮り始めたきっかけみたいなものはあるんですか?
吉野:生まれて最初に映画館で見た映画って、光GENJIの映画だったんです。姉がジャニーズ大好きだったのですよね。それから間があいて大学生になってから、映画を見るようになった。理由は覚えてないんですが、暇だったんですかね。
そのなかで衝撃をうけたのが「マグノリア」。メジャーな映画で、映画としてはもちろんちゃんとしているんだけど、とても自由だった。映画って、こんな自由に作っていいんだ、ってびっくりした。当時、アメリカの映画って、新しい世代の映画監督がどんどん出てきた時期で、デヴィッド・O・ラッセルとか、アレクサンダー・ペインとか、スティーブン・ソダーバーグ。
彼らの映画が日本に来て、映画作りもはじめて数ヶ月かって監督の映画までやってきた。それらを観て、なんとなく「俺、これだったら作れるわ」って思ってしまったんですよね…。でも、一切できない。「何がちがうんだろう」って考えて、つくる。みたいな。いまだにその繰り返しですよね。
壱岐:なるほど。監督って、一生勉強しつづけるものなのかもしれませんね。「マグノリア」は僕も衝撃を受けた映画です。なんじゃこりゃあって思って。あれは驚いた。
大高:落語の題材で映画を撮っている2人がそろって一番感銘を受けたのが「マグノリア」というのはすごいおもしろいですね。何だか最後の蛙のシーンが落語的なものに思えて来ました。
そう考えると、自分たちの世代ってそれこそ、ドラマ「タイガー&ドラゴン」(TBS系)等の影響で落語が「お洒落なもの」としてブームになった世代なので、そこで目を向けていた事もお二人が揃って落語の映画を製作する事に繋がると思うのですが、同時に落語が東西問わず物語るという行為の本質的な所に根が有る事に気づく年代になったという事もあるかもしれませんね。
壱岐:映画って、とにかく映画が大好きで監督になる人と,やむにやまれず消去法で監督になった人がいると思うんですけれども、僕は後者の方ですね。映画は昔から大好きだったんですが、まさか自分で監督までやるとは思っていなかったんです。10代のころはクリーチャーや造型が好きで、アニメーターになろうと思っていたんですよ。美術大学でコンピューター・グラフィックスを学び、カメラマンとしても活動したし、アニメーションも手がけた。充実感もありました。けれども、人と人との繋がりなどもきちんと描写したいと思ったら、手元に映画が残ったという感じでしょうか。
僕が一番最初に観て、記憶に残っている映画っていうのは平成版の「ゴジラ」。その影響もあり、アニメーターを志したのかもしれません。ですが、『ゴジラ』を思い返してみると、造形はもちろん好きなんですけれども、人間物語が濃かったことも強く思い出される。結局は人間のドラマに惹かれていたのかもしれないですね。
安政4年より続く鈴本演芸場での講座シーンロケも敢行「ねぼけ」
これからの映画の作り方
大高:監督の立場から見て、メジャー映画とインディペンデント映画とをわける定義はなんだと感じますか?
壱岐:うーん、僕は単純に予算だと思います。メジャーでも、自主でも優秀な映画、ダメな映画、両方ともでてきているから。メジャーと自主の違いが、良い作品になるかどうかの本質的な原因にはならないと思います。
吉野:僕も、結局どこからお金が出ているか,という話に落ちるような気がするな。
大高:メジャーで映画をつくろうとすると、TVスポットやタイアップは必須でしょうし、そのような規模での製作を支える数値的な裏付けが当然必要になってくると思います。「この原作で、このキャストならこれぐらいの興行を見込める」といった感じで。ただ、映画が難しいなと思うのが、必ずしも結果を読み切れないという点。興行を意識して作家性も抑えた結果、人が見に来てくれなかったらやるせないですよね。
本当は、最初から大当たりを狙うのではなく、ある程度の予算を確保しつつ、ある程度、観に来る人を増やすためのしかけもつくり、そして自分たちの作家の色も出していくというようなバランスの取り方ができると映画にとって幸せな気もします。そういう意識を持った作品群から、時代を作るヒット作品や、先程名前が出たソダーバーグやO・ラッセル等の次代の作家が誕生して来たのだと思います。ただ、人の姿勢も中腰の姿勢が一番厳しいと言われるように、中間的な予算、いわゆるミドルバジェット映画を作り続けるのが一番難しい。
吉野:そういった若手の監督が一定の予算でチャレンジできる商業映画の枠が非常に狭くなっているんですよね。それこそむかしのATGのような枠。それこそ、うまくいえば森田芳光監督みたいな人が出てくるんだけど。現在の映画の予算って、両極端になって、予算が何百万円の映画か、もしくは何十億円となっている。中間がほとんどない。
壱岐:あいだが確かにないですよね。アメリカの配信型ドラマであれば予算的に真ん中ぐらいでしょうか。日本はそういった中堅の作品が経済に直結する文化の土壌が無いので、どんどん先細りになっていっている。
吉野:結局、メジャーでずっと同じ監督が撮り続け、同じ出演者が演じ続けている。何千万円の予算規模作品で、ものすごいヒットするものがあれば、監督や役者にスポットがあたって、次のステップに行けるかもしれない。
壱岐:人材はそれなりに出ていると思うんですが、包括的に育成するバックボーンが骨抜きになっていると感じています。ある層のお客さんには十分知られている監督や俳優なのに、それ以外の市場にはほとんど興味を持たれていない、結果的に客足が伸びそうにもないから配給をためらう、というような取りつく島もない状況もあったりする。映画を取り巻く環境が、刹那的で極端になってきています。
吉野:それでも、「そこのみにて光輝く」(2014年/呉美保監督による佐藤泰志の小説の映画化)があれだけ評価されたのはなんか希望が見えました。こういう映画もちゃんと評価される状況なんだって。ちょっと流れも変わるかも、と思いました。これからのシーンに期待しています。
大高:僕がクラウドファンディングをやろうと思った背景には、そのような一番大変で手を出しづらいミドルバジェット映画、チャレンジングな映画を粗製濫造でない形で作り続けられる環境が重要だと思ったことがあったりします。
クラウドファンディングという文化が根付けば、そのような状況で映画を創る人たちや楽しむ人たち、両方を同時に増やしていけるのではないかと。